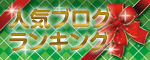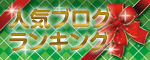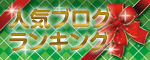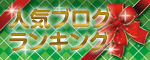2011年03月04日
人間はだれもが、磨けばそれぞれに光る、さまざまなすばらしい素質をもっている。だから、人を育て、生かすにあたっても、まずそういう人間の本質というものをよく認識して、それぞれの人がもっているすぐれた素質が生きるような配慮をしていく。それがやはり、基本ではないか。もしそういう認識がなければ、いくらよき人材がそこにあっても、その人を人材として生かすことはむずかしいと思う。
『松下幸之助 成功の金言365』 3月4日の節より引用
上司と部下あるいは同僚の関係にあっても、相手の素質を見抜けていないことは多いのではないでしょうか。
素質がよくわからないときには、なるべくたくさん話を聴いて、その人の良さを引き出そうと思います。
面談をしたり、他の人と話している姿を見たり、車や電車で一緒に移動したり、食事をしたりして、違う側面にふれてようやく、こういうところがあるのか・・・と気がつくことがあります。
殻に閉じこもって、なかなか開いてくれない人、本当に思っていることを話してくれない人は、私の聴き方がいけないのでしょうけれども、困ってしまいます。
よく分からない人には、大切な仕事を任せることはできません。
人口が増えていた高度成長期と違って、我々はいま縮小する経済の中にいますから、お互いに選び、選ばれる状況にあります。
自分では気がつくことが出来ないよいところは誰にでもあるものです。
上司が部下の素質を引き出す努力をするだけではなく、部下は信頼できる上司に積極的に心を開いていく・・・そんな関係が必要なのではないか、と思います。

参考文献:『松下幸之助 成功の金言365』 松下幸之助 (PHP研究所)
第三回上田ビジネス読書会のお知らせです。
平成23年3月16日水曜日 午前6時半より、上田市のささやにて開催します。課題図書は冨山和彦著『挫折力』です。この本は、立場によって反論異論も出る本だと思いますが、あえて取り上げました。
年齢男女問いません。難しい話はしません。課題図書について、共感できるところ、納得できないところなどをお互いに話し合い、理解を深め、人生に役立てていく会です。詳しくは右のお知らせ欄をご覧ください。
現在の参加者は5人(うち1人は女性)です。
御連絡は右の「オーナーへメッセージ」から、私にメールをください。
ご参加お待ちしております。
参考ブログ:
「『挫折力』を読んで」
http://highlyeffective.naganoblog.jp/e676108.html
「第二回上田ビジネス読書会開催しました。」
http://highlyeffective.naganoblog.jp/e668222.html
Hitoshi Yonezu at 10:00
| 松下幸之助
2011年02月20日
たとえば、腕に一つの小さいできものができると、そのできものが非常に気になる。けれども、今度は腹の一部に大きなできものができたとなると、小さいできものはもう忘れて、大きいほうだけが気になる。そういうものである。
悩みもそれと同じではなかろうか。常に一つに集結する。百の悩みをもっていても、結局、悩むのは一つ。いちばん大きなものに悩みをもつ。そういうものである。
『松下幸之助 成功の金言365』2月20日の節より引用
若いころ真剣に悩んでいたことが、いまとなっては何でもないことになってしまっています。一生懸命考えていた悩みは、いまから見たら本当に小さなことだったのです。
仕事でも十年前に悩んでいたことと、いま悩んでいることは全く違うものです。
松下幸之助さんのおっしゃるように、大きな悩みができれば、小さな悩みは大きなものに集結してしまうのです。
だから、向かってきた悩みに自然に対応していればよいわけで、悩みがどんどん増えていってしまうという心配はしなくていいわけです。
人生のステージに応じて、それなりの悩みがやってくるのだろうと思います。
悩みのレベルが上がったことは、もしかしたら少し喜ばしいことかもしれません。
参考文献:『松下幸之助 成功の金言365』 松下幸之助 (PHP研究所)

Hitoshi Yonezu at 10:00
| 松下幸之助
2011年02月19日
会社とか国が、どうも好ましくないというような状態に陥ったと気づいた場合には、やはり体面を気にせず、躊躇することなく、すぐに治療することが大切だと思う。なすべきときには何でもなさなければならないと思うのである。
『松下幸之助 成功の金言365』2月19日の節より引用
人が病気になると、すぐに薬を飲んだり、手術をしたりして治そうとするのに、会社や国となると世間体を気にして、病気にかかっていることを知られたくないという気持ちが働く、と松下幸之助さんはおっしゃっています。
確かに経営者は体面や風評を気にします。
正直なところ、いつでも景気のいいことを言っていたい、と思います。見たくないものは見ないでおこう、と考えてしまうこともあります。(政治家も同じですか・・・)
そうやって逃げていれば、現実は何も変わりませんし、悪化してしまうこともありえます。
まずは現実を見つめることです。そして、しなくてはならないことは思い切って決断しなくてはなりません。
弱い自分の行動を、よく反省したいと思います。
参考文献:『松下幸之助 成功の金言365』 松下幸之助 (PHP研究所)

Hitoshi Yonezu at 10:00
| 松下幸之助
2011年02月12日
人間は物事を悪くとり、悲しんでいたんでは際限がなく、ついには自殺する人も出てくるものである。それは心の持ち方次第である。成功した人たちの伝記を読んでみると、普通の人なら、その困難に打ち負かされて自殺するようなところを、むしろ反対に喜び勇んでその困難に体当たりしている。
『松下幸之助 成功の金言365』2月12日の節より引用
昨今、大企業の業績がよくなっているというものの、中小企業は依然厳しい環境にあり、この状況はまだずっと続くと思います。
お正月からたくさんの経営者のお客様とお話をいたしましたが、景気がいいという中小企業の経営者は、ごくわずかです。
日本の企業のうち、個人事業者と中小企業が全体の99.7%の割合を占め、中小企業の雇用者数もおよそ7割を占めていると言われています。
業績がよくなったと新聞に書いてあることは、大企業、上場企業のことです。
中小企業、非上場企業は事実上、業績を公開していないところがほとんどですから、新聞で企業業績を見るときには、「大企業では、」と枕ことばをつけて読むのが正しい読み方です。
さて、松下幸之助さんは、成功した人は大変なことが起きても、喜び勇んでその困難に体当たりしていく、といっています。
それは全くその通りだと思います。
問題は、われわれがそのように強く強く心を保ち続けていいられるかということ・・・そこが一番難しいところです。
人のためになれるのなら、と思い、何とか明るく前向きにがんばっていきたいと思います。
参考文献:『松下幸之助 成功の金言365』 松下幸之助 (PHP研究所)
ビジネス読書会、開催します
第二回上田ビジネス読書会は、平成23年2月16日水曜日 午前6時半より、上田市のささやにて開催します。課題図書は酒井穣著『新しい戦略の教科書』です。詳しくは右のお知らせ欄をご覧ください。年齢男女問いません。ご参加お待ちしております。
参考ブログ:
『ビジネス読書会、開催しました!』
http://highlyeffective.naganoblog.jp/e648104.html
「『あたらしい戦略の教科書』を読んで」
http://highlyeffective.naganoblog.jp/e614050.html

Hitoshi Yonezu at 10:00
| 松下幸之助
2011年02月10日
自分を失った人間が百億人おっても、それこそ烏合の衆にすぎない。自己を認識しないで、ただいたずらに他人の真似をしたがるのは、あたかも人間が犬の真似をするのと同じである。そこには何の誇りもない。
お互いに、自分が他人と違う点を、もっとよく考えてみよう。そして、人真似をしないで、自分の道を自分の力で歩んでいこう。そこにお互いの幸福と繁栄の道がある。
松下幸之助著『道をひらく』2月10日の節より引用
いま日本は悲観論で一色ですね。
先日、ある会で、ワールドビジネスサテライトの出演でも有名なNTTデータ経営研究所所長の斉藤精一郎さんの御講演をお聞きしました。
1時間30分の講演の内容のほとんどは、これから日本がいかに大変になっていくのか、という話でした。
日本の年間給与額は、20年前の金額とほぼ同じ、主要国の中でリーマンショック前の株価を越えていないのは日本だけ、のべ13年間ずっと物価が下がっている、TPPで一番大変なのは、中小企業である、日本の財政はあと6、7年しかもたない・・・
最後の10分で、ではどうしたらいいのか、という話になりました。
何か素晴らしい策があるのか?と期待しておりましたら、結局、答えは、海外へ出ていくこと、でした。また、インバウンドを増やしていく策として、アグリツーリズムや農商工連携などをすすめられていました。
やはり、マジックはないのです。このままでいたら、何一つよくなりません。一歩踏み出していかねばなりませんね。
大正七年、松下電気器具製作所を設立したとき、戦後、公職追放などの制限を受けたとき、松下幸之助さんは、どんな気持ちだったのでしょうか。今は松下さんが生き抜いてきた大東亜戦争敗戦と並ぶ大きな変革期だと思います。毎日、松下幸之助さんの言葉を読んでは、当時を想像しています。
参考文献:『松下幸之助 成功の金言365』 松下幸之助 (PHP研究所)
ビジネス読書会、開催します
第二回上田ビジネス読書会は、平成23年2月16日水曜日 午前6時半より、上田市のささやにて開催します。課題図書は酒井穣著『新しい戦略の教科書』です。詳しくは右のお知らせ欄をご覧ください。年齢男女問いません。ご参加お待ちしております。
参考ブログ:
『ビジネス読書会、開催しました!』
http://highlyeffective.naganoblog.jp/e648104.html
「『あたらしい戦略の教科書』を読んで」
http://highlyeffective.naganoblog.jp/e614050.html

Hitoshi Yonezu at 10:00
| 松下幸之助
2011年02月06日
窮境に立つということは、身をもって知る尊いチャンスではあるまいか。得難い体得の機会ではあるまいか。そう考えれば、苦しいなかにも勇気が出る。元気が出る。思い直した心の中に新しい知恵がわいて出る。そして、禍いを転じて福となす、つまり一陽来福、暗雲に一すじの陽がさしこんで、再び春を迎える力強い再出発へ道がひらけてくると思うのである。
松下幸之助著『道をひらく』より引用
苦しい境遇にあるときに、よいことを考えるのは、なかなか難しいものです。
広辞苑によれば、「一陽来復」には次のような解説がありました。
①陰がきわまって陽が帰ってくること。陰暦11月または冬至の総称。
②冬が去り春が来ること
③悪い事ばかりあったのがようやく回復して善い方向に向いてくること。
ここ二三日、急に暖かくなってきて、まさに一陽来復といった感じがします。
しかし、冬が終わったから暖かい春が来るわけではなく、悪いことがあったから次は順番としてよくなる、というわけでもないのです。
厳しい冬の後に冷たい春が来るかもしれませんし、悪いことの次にもまた悪いことがくる、ということもあります。
一陽来復というと、自然に陽が差し込んでくるというイメージがありますが、ここはただじっと待つというのではなく、松下さんがおっしゃっているように、身をもって知る尊いチャンスと考えるべきですし、禍を活用して福へつなげていく、という行動が必要なのです。
冬は冬として前向きにとらえ、チャンスがきたと喜び、自分で切り開いていく、というところが肝心なのではないかと思います。
ビジネス読書会、開催します
第二回上田ビジネス読書会は、平成23年2月16日水曜日 午前6時半より、上田市のささやにて開催します。課題図書は酒井穣著『新しい戦略の教科書』です。詳しくは右のお知らせ欄をご覧ください。年齢男女問いません。ご参加お待ちしております。
参考ブログ:
『ビジネス読書会、開催しました!』
http://highlyeffective.naganoblog.jp/e648104.html
「『あたらしい戦略の教科書』を読んで」
http://highlyeffective.naganoblog.jp/e614050.html

Hitoshi Yonezu at 10:00
| 松下幸之助
2011年01月28日
『ドラッカー 365の金言』によく似た題名と装丁ですが、松下幸之助さんの言葉を集めた『松下幸之助 成功の金言365』という書籍がPHP研究所より出版されました。
PHP研究所の経営理念研究本部の編集で、松下幸之助の50冊を越える著書や発言集、月刊誌などから抜粋した文章をまとめたそうです。
『ドラッカー 365の金言』と同様に、一日一ページですから、毎日少しずつ松下幸之助さんの考え方を学ぶことができます。
うれしかったのは、1,800円(税別)という価格です。
大きさ、紙質、装丁がほぼ同じで、二色刷りというところも同じの『ドラッカー 365の金言』は、2,800円(税別)ですから、1,000円も安いのです。この質感で1,800円は昨今出版される本の価格と比較して非常に価値があると思います。
権利の関係なのか、なぜ安くできたのかはよく分かりませんが、さすが日本的経営だなあ(もう古いですが、松下さんの思い出です)、いいものを安く作るという精神の表れだよね・・・とひとりでうれしくなっておりました。
1月28日の節より文章を引用します。
人間は一面では、自分の意志によって道を求めることもできるけれど、反面、自分の意志以外の大きな力の作用によって動かされているということを考えることも大切なのではないだろうか。もし、そのようなことが考えられるならば、私はそこから非常に力強いものが生まれてくると思う。
『松下幸之助 成功の金言365』 1月28日の節より引用
自分の意志以外の大きな力の作用とは、宗教などの限定されたものではなく、運や宇宙や世界の流れのようなものまで含んだものだと思います。
この大きな力の作用にのるために、諦観すること、いい意味での諦めをもったほうがよいと松下さんはおっしゃっています。
がちがちにならずに、一面、諦めて、流れにのるということ、少し気が楽になりますね。

参考文献:『松下幸之助 成功の金言365』 松下幸之助 (PHP研究所)
参考文献:『ドラッカー 365の金言』 P.F.ドラッカー (ダイヤモンド社)
ビジネス読書会、開催します
第二回上田ビジネス読書会は2月16日水曜日 午前6時半より、上田市のささやにて開催します。詳しい内容や、課題図書については、右のお知らせ欄をご覧ください。年齢男女問いません。ご参加お待ちしております。
参考ブログ:
『ビジネス読書会、開催しました!』
http://highlyeffective.naganoblog.jp/e648104.html
「『あたらしい戦略の教科書』を読んで」
http://highlyeffective.naganoblog.jp/e614050.html
Hitoshi Yonezu at 10:00
| 松下幸之助
2011年01月16日
カンというと、一般的には何となく非科学的で、あいまいなもののように思われるけれども、修練に修練を積み重ねたところから生まれるカンというものは、科学でも及ばぬほどの正確性、適確性を持っているのである。そこに人間の修練の尊さがある。
松下幸之助著 『道をひらく』より引用
優れたサービスパーソンは、お客様のことをよく存じ上げていて、何も言われていなくても、お客様の必要とするものや、お好きなものを、先回りして、次々と揃えてお待ちしているそうです。
何か不都合なことが起こりそうな場合も、鋭い嗅覚で事前に察知して、問題を回避できるのです。
私はこういうものこそ、松下幸之助さんのおっしゃっている、仕事の修練から来たカンだと思います。
私が社員にがっかりすることは、仕事に対してあまりにもカンが働いていない場合です。「○○だったら、△△になるということがわかるだろう!」とよく社員を叱っています。
これはマネジメントで解決できる問題ではなく、その人物の能力や適性が問われることです。
それでも、やる気があって、本当に熱心に取り組んでいるのなら、カンもだんだんと身についてくると思います。
日々漫然と作業をこなしていたり、自分本位で仕事をしていると、お客様がどのようなお気持ちになっているのか、気にならないでしょう。カンが養われません。
カンが働かないような、先が読めない仕事は、ただこなしている仕事となり、お客さまにご満足いただくことはできないでしょう。
うちの社員たちには、日々真剣に仕事をして、カンを身につけてほしいと思います。
しばらく前に、深夜、一人でバーのカウンターで飲んでいたときのことです。
隣に見たことのない中年の紳士が座りました。
その方はとても温和なよい方だったのですが、人の素性を当てたがる癖があるようでした。
私の人となりを見て、変わった商売をしている人物と思ったらしく、
「どちらの○○の親分さんですか?」
と、しきりに聞いてくるのです・・・カン違いですかね・・・

参考文献:『道をひらく』 松下幸之助 (PHP研究所)
ビジネス読書会開きます!
http://highlyeffective.naganoblog.jp/e623163.html
Hitoshi Yonezu at 10:00
| 松下幸之助
2011年01月08日
人より一時間、よけいに働くことは尊い。努力である。勤勉である。だが、今までよりも一時間少なく働いて、今まで以上の成果をあげることも、また尊い。そこに人間の働き方の進歩があるのではなかろうか。
それは創意がなくてはできない。くふうがなくてはできない。働くことは尊いが、その働きにくふうがほしいのである。創意がほしいのである。
松下幸之助著 『道をひらく』より引用
昨日は、弊社の新年第一回目の幹部会議があり、経営の勉強をした後、それぞれのレポートや抱負を発表をしてもらいました。
毎月開催している14の社内会議のうちの一つですが、各部門の責任者が集まりますので、最も網羅的な会議です。
みんな意欲的に仕事に取り組んでくれて、本当にありがたいなあ、と思いました。
毎月毎月、問題を解決しても、次々と新たな問題が出てきて、お客さまにご迷惑をおかけしています。
しかし、一年を通して振り返ってみると、進歩を確信できた部分もありました。
サービス業といえども、創意と工夫によって、お客様のお役にたてるように革新出来ることがたくさんあります。
うちの社員たちには、長時間働いているから・・・と慢心するのではなく、常に創意と工夫を求めていきたいと思います。

参考文献:『道をひらく』 松下幸之助 (PHP研究所)
ビジネス読書会開きます!
http://highlyeffective.naganoblog.jp/e623163.html
Hitoshi Yonezu at 10:00
| 松下幸之助
2011年01月03日
わからなければ、人に聞くことである。己のカラにとじこもらないで、素直に謙虚に人の教えに耳を傾けることである。それがどんな意見であっても、求める心が切ならば、そのなかから、おのずから得るものがあるはずである。
おたがいに、思い悩み、迷い憂えることを恥じるよりも、いつまでも己のカラにとじこもって、人の教えを乞わないことを恥じたいと思うのである。
松下幸之助著 『道をひらく』より引用
若いころは、自分の知らないことを人に聞くのは恥ずかしいことだ、と思っていたことがありました。
自分の無知をさらすのが恥ずかしいという思いがあったのと、人に聞く前にまず自分で調べなさい、と教育された影響もあると思います。
いま、インターネットのQ&Aサイトを見ると、辞書を調べればわかるような簡単なことを無邪気に質問している人がいて、また、そういう質問に対しても丁寧に答えている人がいて、いくらポイントが関係するとはいっても、甘やかしすぎではないかと思ってしまいます。
インターネットで知らない人に質問を投げかければ、答えは返ってくるでしょうが、自分で調べるという力が育ちませんし、出所がはっきりしない答えは、正しい答えとは限りませんから、間違った情報を信じてしまうという危うさもあります。
そういう簡単な問題は別として、仕事のこととなれば、やはりどんなことでも不明なことは聞いてほしいと思います。
よくわからないのに、自分のやり方で進めてしまって、会社の方針や、上司の考えとは全く違ったものになってしまった、という話を聞くことがあります。
私も、どうして途中で相談しなかったんだ!と部下を叱ることがあります。

参考文献:『道をひらく』 松下幸之助 (PHP研究所)
ビジネス読書会開きます!
http://highlyeffective.naganoblog.jp/e623163.html
Hitoshi Yonezu at 10:00
| 松下幸之助
2010年12月29日
他人の道に心をうばわれ、思案にくれて立ちすくんでいても、道はすこしもひらけない。道をひらくためには、まず歩まねばならぬ。心を定め、懸命に歩まねばならぬ。
それがたとえ遠い道のように思えても、休まず歩む姿からは必ず新たな道がひらけてくる。深い喜びもうまれてくる。
松下幸之助著『道をひらく』より引用
他人の人生、家族、仕事、環境・・・とかく人のことは気になります・・・
自分は遅れているのではないか、自分は間違っているのではないか・・・
他人と自分を比較しても、他人のことをどんなに思案しても、何も変わりませんし、何も進みません。
人がどうであれ、自分の道を歩むこと。
自分が歩んできたこの道は、世界にたった一つの道。
よく学び、よく考えて、これだと決めたことを、着実に進めていこう。一歩でも前へ進もう。
奇抜なアイデアを考えたり、一気にジャンプするのではなく、休まず歩む。
難しい世の中だからこそ、歩いていこう、と思ったことでした。
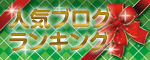
参考文献:『道をひらく』 松下幸之助 (PHP研究所)
ビジネス読書会開きます!
http://highlyeffective.naganoblog.jp/e623163.html
Hitoshi Yonezu at 10:00
| 松下幸之助
2010年12月19日
人間は本来偉大なものである。みごとなものである。しかしそのみごとさは、放っておいてはあらわれない。易きにつくのが人間の情であるとしても、易きがままの日々をくりかえすだけならば、そこにはただ、人間としての弱さが露呈されるだけであろう。
おたがいに与えられた人間としての美しさをみがきあげるために、きびしさを苦痛と感じないまでに心を高めたいものである。
松下幸之助著『道をひらく』より引用
松下幸之助さんは、易きにつくのが人間の情・・・と指摘されていますが、楽な方へ楽な方へと流れてしまうのが、私のような弱い人間の現実です。
やろうと思っていることが、自分の弱さで流れてしまって、いつまでたっても思い通りにいかないのであれば、必ず実行すべきことを自分との約束として、ルールにしてしまったらいかがでしょうか。
そのルールを三ヶ月くらい継続できたら、もう何とも思わない、何の障壁もない、ただの習慣に変わっていきます。
私は本当に弱い人間なので、いろいろなことをルールとして自分に課してきました。私には自分だけしか知らないルールがたくさんあります。
12月は毎日のようにお客様との忘年会があり、私にとっては易きにつきやすい時期だといえます。
自分の生活をよく省みて、また自分にルールを課していきたいと思います。
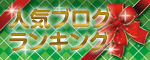
参考文献:『道をひらく』 松下幸之助 (PHP研究所)
ビジネス読書会開きます!
http://highlyeffective.naganoblog.jp/e623163.html
Hitoshi Yonezu at 10:00
| 松下幸之助
2010年12月03日
川にダムが必要なように、暮らしにもダムがほしい。物心ともにダムがほしい。ダラダラと流れっぱなし、使いっ放しの暮らしでは、まことに知恵のない話。
大河は大河なりに、小川は小川なりに、それぞれに応じたダムができるように、それぞれの知恵を働かせれば、さまざまのダムができあがるはずである。
松下幸之助著『道をひらく』より引用
松下幸之助さんのダムの話は有名ですね。
京セラの稲盛和夫さんも、松下さんの講演会でダムの話を聞かれて感動したということを、ご著著で紹介されています。
このダムの話は、教訓としていろいろなことに使えると思うのですが、例えば、最も分かりやすいのがお金です。
稼いだお金をはじから使い果たしてしまうのではなく、いったんせき止めて、人生に有効なことに、だんだんと使っていくということです。
人生で学んだことや経験したことを、その後、有効に活かせるように、ダムにためていきます。
お金でも、学びでも、経験でも、どのようにためて、どのように放出していくのか・・・
いまの生活は流れっ放しではないのか・・・
ダムの話は単純な理屈ですが、「あなたにとってのダムは?」と聞かれれば、はっ、と思うことです。
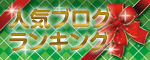
参考文献:『道をひらく』 松下幸之助 (PHP研究所)
Hitoshi Yonezu at 10:00
| 松下幸之助
2010年12月02日
何でもないことだが、この何でもないことが何でもなくやれるには、やはりかなりの修練が要るのである。
平凡が非凡に通ずるというのも、この何でもないと思われることを、何でもなく平凡に積み重ねてゆくところから、生まれてくるのではなかろうか。
松下幸之助著『道をひらく』より引用
新しい事業に挑戦したり、新しい手法を取り入れて既存事業を改革したり、経営者としてはいつも次のことを考えています。
私も、組織が完全ではなくとも、次々にアイデアを出して、新しいことにチャレンジしていた時期がありました。
自分としては揚々と仕事をしていましたが、あまりよい結果は出てきませんでした。
いろいろな区切りがついたとき、また一から淡々と進めていくしかないなあ、と思いました。
何でもないことを何でもなく平凡に積み重ねていく、という松下幸之助さんの言葉の意味を、そのとき、身にしみて感じておりました。
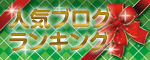
参考文献:『道をひらく』 松下幸之助 (PHP研究所)
Hitoshi Yonezu at 10:00
| 松下幸之助
2010年11月20日
わけ入れば思わぬ道があるというのは、何も野や山の道のことだけではない。いままで、これが一番よいと思っていたものが、やがてもっとよいものができてきて、だから前のものは古くなって、おたがいにさらにゆたかな生活を楽しむことができるようになる。
松下幸之助『道をひらく』より引用
何も変化のないように思える毎日の生活も、十年前のことを思い出せば、ずいぶん変わりました。
いまもし困っていることや解決できそうもないことがあったとしても、ずっとこのまま同じ状態が続くということはないのです。自分も変わりますし、他人も、社会も、経済も、政治も変わってゆきます。
松下幸之助さんは、どんなことにも、もうこれでいいのだ、と安易に考えないで、わけ入れば思わぬ道もあるという思いで歩みをすすめていきたい、とおっしゃっています。
毎日の小さな努力は、着々と積み重なって、形になる時が来る・・・と私も信じております。
これからの十年もあっという間でしょうが、十年後によかったな・・・と思えるように、新しいことに挑戦し、あきらめないで、前向きに明るく考えていきたいと思います。
参考文献:『道をひらく』 松下幸之助 (PHP研究所)

Hitoshi Yonezu at 10:00
| 松下幸之助
2010年11月12日
進むもよし、とどまるもよし。要はまず断を下すことである。みずから断を下すことである。それが最善の道であるかどうかは、神ならぬ身、はかり知れないものがあるにしても、断を下さないことが、自他共に好ましくないことだけは明らかである。
松下幸之助『道をひらく』より引用
毎日、毎時間、どなたであろうと、人生とは決断の連続です。
朝、どのネクタイを結ぼうかと考えるとき、ランチの定食を選ぶとき、車の中で聴くCDを選ぶとき、営業先を回る順序を考えるとき、・・・などなど、分刻みで決断を迫られています。
こういう小さな決断を迷っていたら、先へ進んでいけませんね。
しかし、心の中でもやもやしている面倒なことについては、決断をしなくても、すぐに大きな影響が出てくるわけではないので、先延ばしにしてしまいます。
明日やればいいや、来月にしよう、・・・という甘えが決断を回避させてしまいます。
人にご迷惑がかかるかもしれないこと、面倒なこと、辛いこと、厳しいこと・・・先に伸ばさず、早く決断していったほうがよいですね。
そういうときに「情」が大きくなってしまうと、なかなか決断することができません。経営においても「情」は大切にしていきたいですが、「理」が必要なときもあります。
参考文献:『道をひらく』 松下幸之助 (PHP研究所)

Hitoshi Yonezu at 10:00
| 松下幸之助
2010年10月30日
きょう一日、本当によく働いた、よくつとめた、そう思うときには、疲れていながらも食事もおいしくいただけるし、気分もやわらぐ。ホッとしたような、思いかえしても何となく満足したような、そして最後には「人事をつくして天命を待つ」というような、心のやすらぎすらおぼえるものである。
松下幸之助『道をひらく』より引用
今日は台風14号の影響で、信州上田は朝から大雨です。みなさまどうか災害にご注意くださいませ。
お足もとの悪い中、たくさんのお客様がうちのお店に来てくださいます。本当にありがとうございます。
一日よく働いて、松下幸之助さんのような気持ちになることができたら、幸せです。
松下幸之助さんの『道をひらく』は、このブログでときどきご紹介しておりますが、よい本と知って、ご自分でお買い求めになったという話をときどきお聞きします。うれしいことです。
参考文献:『道をひらく』 松下幸之助 (PHP研究所)
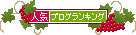
Hitoshi Yonezu at 10:00
| 松下幸之助
2010年10月25日
自己を捨てることによってまず相手が生きる。その相手が生きて、自己もまたおのずから生きるようになる。これはいわば双方の生かし合いではなかろうか。そこから繁栄が生まれ、ゆたかな平和と幸福が生まれてくる。
松下幸之助『道をひらく』より引用
コヴィー博士の『7つの習慣』には、「理解してから、理解される」という教えがあります。
自分のことを分かってほしい、自分の言うことを聞いてほしい、という前に、まず相手のことを知ろうとする、相手のことを理解する方が先だ、ということです。
この部分で私は大きな気付きを得ました。詳しくは『7つの習慣』を読んでみてください。
引用した松下幸之助さんの文章も、同じことを意味していますね。
人によっては、自分の主張を通し、自分の好きなことばかりをしゃべり続けて、相手には意見をはさませず、その場を支配して、平気な顔をしている人もいます。
その場はそれでよいでしょうが、二度三度と続くと、周りの人の心は離れていってしまいます。
私のような経営者や組織のトップに立つ人は、こういうことが通る立場にいますから、裸の王様にならないように気をつけなければなりません。
ビジネスの場であれ、プライベートな場であれ、私一人がようようとしゃべっていて、周りが黙っていると、みんな聞いていてくれるのかな?楽しいと思っているのかな?と、ふと我に返る時があります。
参考文献:『道をひらく』 松下幸之助 (PHP研究所)
『7つの習慣』 スティーブン・R・コヴィー (キングベアー出版)
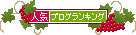
Hitoshi Yonezu at 10:00
| 松下幸之助
2010年09月28日
素直さを失ったとき、逆境は卑屈を生み、順境は自惚を生む。逆境、順境そのいずれをも問わぬ。それはそのときのその人に与えられた一つの運命である。ただその境涯に素直に生きるがよい。
素直さは人を強く正しく聡明にする。逆境に素直に生き抜いてきた人、順境に素直に伸びてきた人、その道程は異なっても、同じ強さと正しさを聡明さを持つ。
松下幸之助『道をひらく』より引用
私は、若いころは、あまり素直な人間ではありませんでした。
人から言われたことを素直に聞くよりも、自分の考えを主張して通した方がよいことなのだ・・・と信じていました。
なぜそういう風に考えるようになってしまったのかは、よく分かりません。
いろいろな本を読んで勉強して、少し大人になったと錯覚して、いきがっていたのでしょう。アメリカ関係の本をたくさん読んでいたので、まずは主張するというアメリカの考え方に感化されてしまったのかもしれません。
まだ小学生のころは、素直だったかもしれませんが、高校大学と進学するにつれて、少々生意気な若者になってしまっていたと思います。
いまではいろいろな経験をして、素直がよい、ということを理解しました。私一人の頭で出来ることなんて、本当にちっぽけなことです。人さまの話はありがたいことです。
ときどき若者とお話をして、素直な方だと、立派だな~と思いますし、自分の意見を押し通そうとする方を見ると、昔の自分のようだな・・・と思っています。
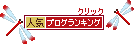
参考文献:
『道をひらく』 松下幸之助 (PHP研究所)
Hitoshi Yonezu at 10:00
| 松下幸之助
2010年09月18日
人と人が相寄ってつくった組織。商店、会社、いろいろの団体。一番大きいのが国家の組織。それらの末端をちょっとつついても、すぐにピンとくるかどうか。間髪入れずの反応が示せるかどうか。合理化といい生産性の向上といっても、本当はこの間髪入れずの反応が示せる体制から生まれてくるのである。
松下幸之助著『道をひらく』より引用
松下幸之助さんは、どこをつついてもピンと頭に伝わってくる人間の身体の複雑な仕組みを引き合いにして、組織も同様にどこをつついてもピンとくる体制づくりが必要である、とおっしゃっています。
うちのような小さな会社でも、お客様との接点、最前線で起こっていることが、私まで伝わっていないということがあります。
このままでは、経営がよくなっていきませんし、お客さまにますますご迷惑をおかけしてしまいます。
感度がよく、気がきく社員を育てていくことは大切なことですが、社員の教育というのは時間がかかりますし、新人もどんどん入ってきますから、水準を保っていくのは容易なことではありません。
大前提として社員の教育は継続しながら、まずは、ピンとくるような仕事の仕組みをつくることではないかと思います。
仕組みをつくって運用していくことが、社員たちの感度を上げることにつながっていくのではないかと考えています。
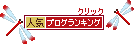
参考文献:
『道をひらく』 松下幸之助 (PHP研究所)
Hitoshi Yonezu at 10:00
| 松下幸之助
2010年09月07日
懸命な思いこそ、起伏があろうと、坦々としていようと、ともかくもわが道を照らす大事な灯なのである。
松下幸之助著『道をひらく』より引用
人は自分が信じてもいないことに、努力できるはずがありません。強烈な願望を描き、心からその実現を信じることが、困難な状況を打開し、ものごとを成就させるのです。
稲盛和夫著『心を高める、経営を伸ばす』より引用
松下幸之助さんは松下電器産業、現在のパナソニックの創業者で、戦後の日本経済をけん引した伝説の経営者です。
稲盛和夫さんは、京セラを創業した偉大な経営者で、いまは、請われて日本航空の再生に取り組んでおられます。
稲盛さんの御本には、松下さんの話が出ててきます。どういうご関係だったのか詳しくは分かりませんが、京セラがいまほどの大企業ではなかったころから、稲盛さんは松下さんから学んでこられたようです。
そういうつながりあるからでしょう、松下さんの書かれたものと稲盛さんの書かれたものには、近しさを感じます。私は御本を拝読して、お二人の考え方を大切に学んでおります。
いまでは、日本的経営という言葉は死語になりつつありますが、制度とか方法のことではなく、偉大な日本の経営者が考えていることこそが、日本の経営ではなかろうか・・・そんなことを考えておりました。
参考文献:
『道をひらく』 松下幸之助 (PHP研究所)
『心を高める、経営を伸ばす』 稲盛和夫 (PHP)
Hitoshi Yonezu at 10:00
| 松下幸之助
2010年08月26日
むつかしいことかもしれないが、自分の仕事に誇りを持ち、自分の働きに意義を感じるならば、わが身の処し方もおのずから見いだされてくるだろう。
どんな世の中になっても、あわてず、うろたえず、淡々として社会への奉仕を心がけてゆこう。その姿自体が、人びとによってすでに大きな励ましとなり、憩いとなるのである
花のように。泉のように。そこにわれわれの喜びもある。
松下幸之助『道をひらく』より引用
私の入会しているロータリークラブにも、職業奉仕という考え方があります。自分の職業を律し、道徳的水準と品位を高めると共に、業務を通じて職場や地域に奉仕をしていく活動です。
仕事を一生懸命行うことが、社会への奉仕となるという考え方です。
松下幸之助さんの『道をひらく』は、見開き2ページずつで一つの話が完結している本ですが、この中で私が最も好きな話は、「サービスする心」です。松下さんの仕事にたいする考え方をもっともよくあらわしているエッセイだと思っています。
今日ご紹介した「花のように」というエッセイも、同じことをおっしゃっていると思います。
このところ、一時、83円台まで円高が進み、その他にも先行き心配することはたくさんあります。松下さんのおっしゃる、「どんな世の中になっても」・・・がいま来ているともいえます。
それでも、悲観的にならずに、淡々と、やるべきことをやっていく・・・
人のために出来る限りの力を尽くしていく・・・
その姿は、確かに、殺伐としたところに、健気に、そして毅然と咲く、一輪の花といえましょう。
参考ブログ:
『サービスする心』
http://highlyeffective.naganoblog.jp/e455351.html
『サービスする心 その二』
http://highlyeffective.naganoblog.jp/e499576.html
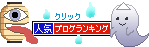
参考文献:『道をひらく』 松下幸之助 (PHP研究所)
今日の信濃毎日新聞の10ページにこのブログが紹介されています。
あんなみっともないものを出して頂いて・・・大変恐縮です。
ありがとうございました。
Hitoshi Yonezu at 10:00
| 松下幸之助
2010年08月20日
死を恐れるのは人間の本能である。だが、死を恐れるよりも、死の準備のないことを恐れたほうがいい。人はいつも死に直面している。それだけに生は尊い。そしてそれだけに、与えられている生命を最大に生かさなければならないのである。それを考えるのがすなわち死の準備である。そしてそれが生の準備となるのである。
松下幸之助『道をひらく』より引用
今年の夏は大変な猛暑で、体調を崩されている方には本当に厳しい毎日でございます。どうかお大事になさってくださいませ。
この夏、いくつかの訃報を受け、弔問させて頂きました。また、新盆にも十件ほどのお宅にお邪魔いたしました。
ご遺族にお悔みを述べ、お位牌やお写真を拝見すると、この方とはこういうことがあったなあ・・・こういう話をお聴きしたなあ・・・と様々な思い出が蘇ってきました。
現実にあったことは、昨日のことのように鮮明に思いだせるのに、もう二度と体験することのできない思い出になってしまったのです。
逝かれてしまったということなんだなあ・・・亡くなる前には、どんな思いをされていたのだろう・・・としみじみ想像しておりました。
松下幸之助さんは、死の準備は、それすなわち生の準備であるとおっしゃっています。
私には死の準備など、遠いことのように考えてしまっていますが、実は、これからこうしよう、ああしようと、人生の計画を立てていることこそが死への準備にほかならない、とおっしゃっているのです。
日々の生活や仕事をするということが、死へ進む準備をしているということ・・・
考えておきたいことです。
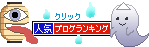
参考文献:『道をひらく』 松下幸之助 (PHP研究所)
Hitoshi Yonezu at 10:00
| 松下幸之助
2010年07月23日
仕事というものは勝負である。一刻一瞬が勝負である。だがおたがいに、勝負する気迫をもって、日々の仕事をすすめているかどうか。
松下幸之助『道をひらく』より引用
松下幸之助さんは仕事を勝負だとおっしゃっている。
会社の経営も、経営戦略というように、戦略・・・つまり戦争の考え方から来ているのである。
私は幸いなことに戦争に巻き込まれた経験はないが、もし世の中が戦争状態だったらどうだろう。
外に出たら、前後左右周りを伺いながら、空を見上げながら、相当用心しなくてはならない。自軍の状況、敵軍の状況をよく把握して、攻める時には一気に攻めていくだろう。
そういう緊張感を仕事の中でもてるだろうか。
松下さんは、昭和40年代に一刻の油断もならぬ状態とおっしゃっているが、今はもっと緊迫した状態ではないか。
昨日と何も変わることなく、ぼーっと仕事をしているようでは、緊張感は生まれてこない。
自分の精神をみつめ、今のままでよいのか?と気持ちを切り替える時間をもちたい。

参考文献:『道をひらく』 松下幸之助 (PHP研究所)
Hitoshi Yonezu at 10:00
| 松下幸之助
2010年07月17日
断じて行なえば、鬼神でもこれを避けるという。困難を困難とせず、思いを新たに、決意をかたく歩めば、困難がかえって飛躍の土台石となるのである。要は考え方である。決意である。困っても困らないことである。
松下幸之助『道をひらく』より引用
長い人生ですもの、楽もあれば、苦もありましょうに。
いまは世の中が大きく変わろうとしているときである。困難があって当たり前の時代である。
松下幸之助さんは素晴らしいことをおっしゃった。
困っても困らないこと・・・ ? ? ?
困ったことが起こっても、
「よーし、きたな!やるぞ~解決するぞ!」と前向きにとらえて、
困ったことだと思わなければよいのだ。
そう思えるには、その前に固い決意が必要だ。
いまは、明治維新、大東亜戦争の敗戦と同程度の、大きな時代の転換点だと言われている。
しかし、少なくとも、明治時代、敗戦より、世の中は幸せだ。
明治時代だって、45年の間に、日清戦争、日露戦争と戦争が続いていたのだ。韓国併合も行われた。
現在は、敗戦以降65年間、戦争には巻き込まれずにすんでいる。
やれることはまだまだたくさんある。よい仲間とともに平成のこの困難を乗り越えていきたいものだ。

参考文献:『道をひらく』 松下幸之助 (PHP研究所)
Hitoshi Yonezu at 10:00
| 松下幸之助
2010年06月24日
まえに、松下幸之助さんの「サービスする心」というエッセイをご紹介ました・・・
参考ブログ:『サービスする心』
http://highlyeffective.naganoblog.jp/e455351.html
松下さんの「サービスする心」というのは、おまけをするとか、無料にするとか、そういう意味ではなくて、自分の持っている力を存分に相手に与えなさいということなのです。
力のある人は力で、頭の良い人は頭で、商売人は商売で、・・・自分が最も得意とすることを、相手のため、社会のために精いっぱいサービスせよ、といいます。
うちの会社にもいろいろな人が働いていますが、それぞれが自分の得意な力を最大限に発揮して、お客さまのお役にたつこと、これがサービスです。
仕事だけではなく、社会的活動や、ボランティアや、道端での出来事など何でも含みます。いつでもどこでも自分の力を発揮していく・・・
相手の方やお客さまに不安を与えてしまったり、最高の提案ができなかったり、まあまあだと思われてしまったら、よいサービスをしたことということにはならないのです。
サービスをすることで相手も社会も繁栄していきます。
自分のもてるもので、精いっぱいのサービスをする・・・
サービスする心・・・
自分はどのように仕事をすべきなのか?と考えたとき、これだ!と思える言葉です。

参考文献:『道をひらく』 松下幸之助 (PHP研究所)
Hitoshi Yonezu at 10:00
| 松下幸之助
2010年06月02日
学ぶ心さえあれば、万物すべてこれわが師である。
語らぬ木石、流れる雲、無心の幼児、先輩の厳しい叱責、後輩の純情な忠言、つまりはこの広い宇宙、この人間の長い歴史、どんなに小さいことにでも、どんなに古いことにでも、宇宙の摂理、自然の理法がひそかに脈づいているのである。そしてまた、人間の尊い知恵と体験がにじんでいるのである。
松下幸之助『道をひらく』より引用
仏教には一切衆生悉有仏性(いっさいしゅじょうしつうぶっしょう)」という言葉があります。
この世に存在するすべてのものに、仏の心があると説いているのです。
日本人は昔から、そこに存在するすべてのものに心があり、学ぶことがあると考えてきました。
ふと感じる何気ないことにも、自分に対する教えがあります。この瞬間に感謝して生きていきたいと思います。
参考ブログ:『なぜ月にウサギがいるの?』
http://highlyeffective.naganoblog.jp/e437646.html

参考文献:『道をひらく』 松下幸之助 (PHP研究所)
Hitoshi Yonezu at 10:00
| 松下幸之助
2010年05月25日
傘も持たないで自分だけはぬれないような虫のいいことを考えているならば、やがてはどこかでつまずく。つまずいてもかまわないというのなら何もいうことはないけれど、人はともかく、つまずいたその原因を、他人に押し付けて自分も他人も不愉快になる場合が多いから、やはり虫のいいことは、なるべく考えないほうがいい。
松下幸之助『道をひらく』より引用
人さまの景気のいい話を聞いていると、なんだか自分も簡単にできるような気持ちになってしまうことがあります。
商売がうまくいきますよ~という、社長が喜びそうなEメールやダイレクトメールも毎日のように来て、どんな話なのだろう?と中をのぞいてみることもあります。
しかし、松下さんのおっしゃるように、世の中にそんなに虫のいい話はないのです。
人の言われるままに動いて、その結果、うまくいかなかったら、動くと決断したのは自分だったはずなのに、きっと人のせいにするでしょう。
自分だけ努力も苦労も省いて、簡単に成功するということはないのです。人のやっていることが楽そうに見えても、実は相当な積み重ねの上に、いまがあるはずです。
虫のいいことを考えない。
楽な道を選びそうになったら、思い出したいことです。

参考文献:『道をひらく』 松下幸之助 (PHP研究所)
Hitoshi Yonezu at 10:00
| 松下幸之助
2010年05月20日
せっかくの九十九パーセントの貴重な成果も、残りの一パーセントの止めがしっかりと刺されていなかったら、それは始めから無きに等しい。もうちょっと念を入れておいたら、もうすこしの心くばりがあったなら-あとから後悔することばかりである。
おたがいに、昔の武士が深く恥じたように、止めを刺さない仕事ぶりを、大いに恥とするきびしい心がけを持ちたいものである。
松下幸之助 『道をひらく』 より引用
うちの社員の仕事ぶりを見ていると、詰めが甘いと思われる者がときどきいる。
もう少し丁寧に仕事をする。
もう一回、確認する。
きれいに整理する。
曲がっているものはまっすぐに直す・・・
こういった小さいことができていない。
大雑把な人は性格を直すこと。仕事は小さなことの積み重ねだ。一つ一つのことを几帳面にしなくてはならない。心に乱れのある人は、小さな仕事に乱れが見える。
私はどんなに神経質だと言われようが、小さなことをきちんとする仕事をしたい。
自分の家族のことだったらどうか。自分の家業だったらどうか。自分のことだったらいい加減にできないはずだ。
うちの社員たちには、家も仕事も区別なく、同等に大切に思い、最後までしっかり見届け、最後の一秒まで気を張り詰めて仕事をしてほしい。

参考文献:『道をひらく』 松下幸之助 (PHP研究所)
Hitoshi Yonezu at 10:00
| Comments(2) | 松下幸之助
2010年05月14日
ものの道理について真剣に叱る、また真剣に叱られるということは、人情を越えた人間としての一つの大事なつとめではあるまいか。叱られてこそ人間の真の値打ちが出てくるのである。叱り、叱られることにも、おたがいに真剣でありたい。
松下幸之助『道をひらく』より引用
会社の社長という立場にいると、お客さまに叱られることは別として、社内において仕事のことで叱られることはほとんどなくなっていく。部下が上司である社長を叱る、ということは普通はありえないからだ。
だから、社外の友人や、コンサルタントの先生など、本当のことを言ってくださる方は、本当にありがたい存在なのだ。こういう人がいないと、社長という人物は、裸の王様になってしまう恐れがある。
私はかつて、ある先生から「社員をもっと叱りなさい!」と叱られたことがあった。
それまでの私は、社員に対して少々甘かった。自分では叱っているつもりだったが、見る人から見たら、ただの優しい社長だったのだ。
社員や会社のことを真剣に思うなら、真剣に叱って、間違ったことは許さず、つめていかねばならない。
松下幸之助さんは、叱ることを「人情をこえた人間としての一つの大事なつとめであるまいか」とおっしゃっている。
情をかけて、叱ることを躊躇していたら、人間としてのつとめを果たさないことになる。
私も、叱られたからこそ気づきがあった。

参考文献:『道をひらく』 松下幸之助 (PHP研究所)
Hitoshi Yonezu at 10:00
| Comments(2) | 松下幸之助