2012年04月23日
部下や家族の間違いを叱るときには、ときには感情をためて怒ることがあってもよいのですが、それはあくまで手段であって、基本的には自分の人格で、冷静に叱るべきではないか、と思います。
つねに感情の波にのって怒っている人は、周りの人から怖がられるようになって一応の上下関係のようなものは出来るでしょうが、しょせん恐怖政治に過ぎないわけです。長期的な関係にはなりえません。
コヴィー博士の『7つの習慣』より引用します。
あなたの人格は常に周囲に向かって発信しており、長期の人間関係においては、相手はそこからあなたとあなたの行動を、本能的に信頼するかしないか決めているのである。
もしもあなたに一貫性がなく、熱したり冷めたり、怒ったかと思うと優しくなったり、あるいは私生活と公の生活とが一致していないような人間だったら、あなたに本当の気持ちを打ち明けることなど、とても私には出来ない。
『7つの習慣』より引用
どんなに怖い人でも、言行が一貫していて信頼できる人格の方であれば、周りから尊敬され長期的な信頼関係を築くことができるでしょう。
会社でも怖い先輩が慕われていることがよくあるもので、よく聞いてみると、仕事上で助けてもらっていることは当然として、見えないところで補うこともきちんとできているのです。
感情にまかせてでしか怒ることができない人はやがて周りの人たちから「また怒るだろうから、いまはとりあえず聞いておこう・・・・・」と見透かされてしまいます。
そういう方はおそらくコミュニケーションが苦手なのではないかと思います。
相手に信頼して頂けるように自分がしっかりすること、自分の人格の土台を築くことがまずは大切だ、ということです。


参考文献:『7つの習慣』スティーブン・R・コヴィー(キングベアー出版)
参考ブログ:「あなたの人格は常に周囲に向かって発信している」
http://highlyeffective.naganoblog.jp/e328822.html
Hitoshi Yonezu at 10:00
| 7つの習慣
2012年03月24日
『7つの習慣』の第一の習慣は「主体性を発揮する」というものです。
主体性とはよく聞く言葉だが、定義があいまいになっている場合が多い。主体性を持つということは率先力を発揮するだけではなく、人間として自分の人生に対する責任をとるということである。私たちの行動は周りの状況からではなく、私たち自身の選択によって決まるのだ。私たちは感情を価値観に従わせることができる。そして、物事を成し遂げる率先力を発揮する責任を負っているのだ。
『7つの習慣』より引用
主体的の反対語は「反応的」であるといわれています。自分で判断せずにすぐに周りのことに反応してしまうからでしょう。
私の人生は、親のせいでもなく、会社のせいでもなく、学校のせいでもなく、先生のせいでもないわけです。
運命によってたとえ何かを引き受けなくてはいけないとしても、それも誰のせいではなく、すべて自分の責任で決めたことです。
過去に何かあったとしても過去は変えられませんから、頭の中に何か過去のことがあるとしたら、すっぱりと諦めるか、置き去りにするかしかありません。
楽しいのも悲しいのも幸せなのも不幸なのも、すべて自分で責任を引き受けるということです。
すべての責任を自分で引き受けてみようと覚悟したとき初めて、主体性のある人生になるのだと思います。
春になると思い出す高濱虚子の俳句をご紹介いたします。
春風や闘志いだきて丘に立つ 高濱虚子

参考文献:『7つの習慣』 スティーブン・R・コヴィー (キングベアー出版)
Hitoshi Yonezu at 10:00
| 7つの習慣
2012年03月14日
昨日あるお客さまが「私の一冊」という企画で取材に来てくださいました。
その会社が発行しているニュースレターで、各社の社長の人生や価値観を変えた一冊の本を紹介するというコーナーを設けるのだそうです。
あらかじめその話を頂いて「何の本にしようかな~」と考えたのですが、真っ先に浮かんできたのがコヴィー博士の『7つの習慣』でした。
その他、稲盛和夫さんや森信三さんの本も考えたのですが、分かりやすく受けられやすい本はやはり『7つの習慣』だろうと思いました。
インタビューを受けながらページをぱらぱらめくってどこがいいのか説明したのですが、めくればめくるほどよい場所が出てきました。
「心に残った文章はどこですか?」と聞かれたときには「たくさんありすぎちゃって」と答えるしかありませんでした。
やはりよい本です。
先ほど『7つの習慣』をとりだして、ぱっと開いたら「誠実」についての部分が出てきたのでご紹介します。
誠実さは正直という概念を含んでいるが、それを超えるものである。「正直」とは真実を語ることである。つまり、言葉を現実に合わせることである。それに対して「誠実さ」とは、現実を言葉に合わせることである。つまり、約束を守り、期待に応えることなのだ。そして、誠実さを持つには統一された人格が必要なのである。
誠実さを示す重要な方法のひとつは、その場にいない人に対して忠実になることである。そうすることで、その場にいる人々との間に信頼が育成される。その場にいない人を弁護することは、その場にいる人との信頼を保つことになる。
『7つの習慣』より引用
私は誠実について聞かれると、この部分を思い出して説明することにしています。
みなさまもぜひご参考になさってください。
(今日はホワイトデーですね。よい一日を!)

参考文献:『7つの習慣』 スティーブン・R・コヴィー (キングベアー出版)
Hitoshi Yonezu at 10:00
| 7つの習慣
2012年03月12日
原則中心の場合、ころころと変わる人や物に頼るようなほかの中心とは違い、安定性は原則の不変性に基づくものになる。そして継続的にそれに頼ることができる。
原則は何に対しても一切反応することはない。怒ることもなければ、私たちに対する態度や接し方を変えることもない。離婚を申し出ることもなければ、逃げることもない。そして私たちをこらしめようとしているのでもなければ、近道や応急処置への甘い誘いもしない。またその正当性はほかの人の行動、周りの環境、今の流行に依存しているものでもない。原則は死ぬこともない。今日あって、明日はないというようなものでもない。火災、地震、盗難によって破壊されることもない。
『7つの習慣』より引用
『7つの習慣』の「第二の習慣」は「目的をもって始める」というものです。
その中の大切な教えは「原則中心の生活をおくる」ということです。
引用した文章でコヴィー博士が説明しているように、原則とは、とても強固で盤石なものです。
原則中心の生活は、自分の安定性、方向性、知恵、力の土台となるのです。
いかなる問題が起ころうとも。原則中心に生きることができていれば、自分らしい解決の糸口が見つかると思います。
では、その原則とは何か?といえば、呪文のようにどこかに分かりやすく書いてあるものではありません。
自分で考えてつくる自分の生き方、理念、哲学です。『7つの習慣』でいえば「個人的なミッションステートメント」こそが「原則」です。
私も『7つの習慣』で学んで、10年くらい前に個人的なミッションステートメントを書きました。その間の自分の成長もあったので、そろそろ見直してみたいと思っています。
個人的なミッションステートメントの書き方については『7つの習慣』に解説されていますから、ご参考になさってください。

参考文献:『7つの習慣』 スティーブン・R・コヴィー (キングベアー出版)
Hitoshi Yonezu at 10:00
| 7つの習慣
2010年09月05日
反応的な言葉がなぜ重要な問題なのかというと、それが心理学でいう「自己達成予言」になるからである。つまりそういう言葉を使う人は、決定づけられているというパラダイムをさらに強く持つことになり、その信念を支える証拠を自分でつくり出すことになる。ますます被害者意識に陥り、生活のコントロールを失い、自分の人生を自分でつくり出す能力を失くしてしまうのだ。そして、自分の状況をすべて外的な要因(他人、環境、星座に至るまで)のせいにするのである。
『7つの習慣』より引用
自分には責任がなく、すべては自分以外の人や環境のせいだと考える人は、反応的な言葉を発することが多くなる。
反応的な言葉とは、何かの事態に対して、自分の意思や想いを加えることなく、一般的に植え付けられたイメージとして出てくる言葉だ。
無理だ・・・
○○でないとだめだ・・・
○○でさえあったら・・・
どうしようもない・・
しなくてはならない・・・
疲れた・・・
これに対して、主体的な言葉とは、何が起こっても、自分が主体的に選択した結果として発する言葉である。
やってみる!
○○がいい!
○○するぞ!
次の案を出すぞ!
そうすることに決めた!
充実している!
反応的な言葉ばかりを話す人・・・反応的な人・・・と話していると、こちらまで暗くなり、元気がなくなってくる。耳を閉じたい気持ちになってくる。
主体的な言葉を話す人・・・主体的な人・・・と話していると、どんな状況であっても、よいことがあるぞ、先は明るいのだ、と思えるようになる。
そういう人と友達になりたい。
宗教的でもなく、心理学でもなく、ただ純粋にそう思うから・・・
明日のブログではこのことと同じことを言っている日本人の先生を御紹介します。
参考文献:『7つの習慣』 スティーブン・R・コヴィー (キングベアー出版)
Hitoshi Yonezu at 10:00
| 7つの習慣
2010年05月02日
大切に思う人々を深く理解するために投資する時間は、開かれたコミュニケーションという形で大きな配当をもたらす。家族や夫婦を襲う問題の多くが、悪化し大きくなる前に止められる。コミュニケーションが円滑にとれていれば、問題は発生段階で解決できる。そして、出てくる問題に対応するだけの大きな信頼残高を、貯えることができるのだ。
『7つの習慣』 第五の習慣の章より引用
夫婦も、父母も、子供も、大切な家族とはいっても、別の人格をもつ他人である。
自分は理解していると思っていても、実は理解できていないことがほとんだ。理解していると思いこんでいるだけである。
会社の上司、同僚や、友人だったらどうだろう。もっと理解できていないはずだ。長い時間を共有していて、思い出や記憶はたくさんあっても、それは相手を理解していることとはあまり関係がない。
相手を理解するためには、コヴィー博士のおっしゃるように、相手を理解するために時間を投資していくことだ。
一対一の時間をもち、お互いの話を聴く。
アドバイスしようとせずに、ただ聴いてみる。
そこから真の円滑なコミュニケーションが生まれ、強い信頼関係へとつながる。

参考ブログ:『相手を理解するために』
http://highlyeffective.naganoblog.jp/e456132.html
参考文献:『7つの習慣』 スティーブン・R・コヴィー (キングベアー出版)
Hitoshi Yonezu at 10:00
| Comments(0) | 7つの習慣
2010年04月29日
話をしているとき、ほとんどの人は、理解しようとして聞いているのではなく、答えようとして聞いているのだ。話しているか、話す準備をしているか、二つにひとつである。聞いている話をすべて、自分のパラダイムというフィルターを通して、自分の自叙伝を相手の生活に映し出しているだけである。
『7つの習慣』より引用
この文章に初めて出会ったとき、私にとっては衝撃的で、「こりゃあ自分のことを言われているなあー」と反省したのを覚えている。
その頃の私は、人の話を聞くふりをしながら、頭の中では、「次に何を話してやろうか」ということばかりを考えていた。
何か相談を受けても、
「その話は、自分の体験では・・・」
「自分にもそういうことがあったぞ、あの時は・・・」
「そのパターンはこうやればうまくいくはずだ・・・」
というように、自分のパラダイムの中で、自分の自叙伝の中で、何か教えてやろう、という態度で話を聞いていた。
つまり、聞いていたのでなく、話す準備をしていたことになる。
しかし、相手の方は、話を聞いてほしかったのだ。
何の偏見もない状態で、何の準備もしないでいいから、ただ純粋に、話を聞いてほしかったのだ。
このことに気づかされて、「聞く」が「聴く」になり、やがて、「傾聴する」という言葉の意味が理解できるようになってきた。

参考文献:『7つの習慣』 スティーブン・R・コヴィー (キングベアー出版)
Hitoshi Yonezu at 10:21
| Comments(0) | 7つの習慣
2010年04月23日
人間関係づくりに最も大切な要素は、私たちが何を言うか、何をするかということではなく、私たちはどういう人間であるかということである。そして、私たちの言葉や行動が自らの中心(人格主義)からではなく、うわべだけのテクニック(個性主義)に起因するものであれば、人は私たちの二面性を感じとることだろう。そういうやり方では、効果的な相互依存関係をつくり上げ、維持するための土台は絶対にできない。
人間関係に大きな力を発揮するテクニックが本当にあるとすれば、それは真に自立した人格から自然にあふれ出るものでなければならない。
『7つの習慣』より引用(青字にしたのは私です)
若いころは、初対面の人と会うと、妙にへつらってしまったり、偉そうな態度をとってしまったり、無関心を装ってしまったりしていた。
お客さまを接待する商売をしていながらこんなことを言うのは本当に恥ずかしいことだが、正直なところ、知らない人と、どうやって人間関係、信頼関係をつくっていけばいいのか、よく分かっていなかった。それはそれは遠い道のように思えたのだ。
しかし、私もいろいろ経験し、少し成長したので、いまではそういう悩みも無くなった。
そして、尊敬できる皆さま方とお話をさせていただくことができるようになった。
コヴィー博士が書いておられるように、自分がどういう人間であるかということが、人間関係をつくっているからである。
人間関係はいまこれから考えながらつくるものではなくて、もう何年も前からだんだんと出来あがってきているのである。
どこへ行こうが、誰と会おうが、そのままの自分でいるしかない。
自分そのものが自分の人間関係なのである。
人間関係がぎくしゃくしているな~、良い友達がいなくなってきたな~、思ったら、自分の人格を変えていくしかないのである。
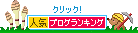
参考文献:『7つの習慣』 スティーブン・R・コヴィー (キングベアー出版)
Hitoshi Yonezu at 10:00
| Comments(0) | 7つの習慣
2010年04月06日
リーダーシップとは人を惹きつけることではない。惹きつけるだけでは扇動者にすぎない。友だちをつくり、影響を与えることでもない。それでは人気取りにすぎない。
リーダーシップとは、人のビジョンを高め、成果の水準を高め、人格を高めることである。そのようなリーダーシップの基盤として、行動と責任についての厳格な原則、成果についての高度な基準、人と仕事に対する敬意を日常の実践によって確認していく組織の精神に勝るものはない。
『ドラッカー 365の金言』 4月6日の節より引用
いつものことながら、わざわざ難しく翻訳されてしまっているドラッカーです。一字一句そのまま引用しておりますが、最後の一文などは非常に読みずらいです・・・
「人と仕事に対する敬意を」のあとに句点が入れば少し読みやすくなるでしょうか。
ドラッカーによれば、カリスマ性がなくてもリーダーにはなれるのです。以下の3点を日々の実践によって確認していくことです。
1.行動と責任についての厳格な原則
2.成果についての高度な基準
3.人と仕事に対する敬意
これによって、以下の3点を高められるようになり、それがリーダーシップだといっています。
1.人のビジョン
2.成果の水準
3.人格
ドラッカーのリーシップ、私にとって、道のりは遠いですが、たゆまず努力致します!!!

参考文献:『ドラッカー 365の金言』 P.F.ドラッカー (ダイヤモンド社)
Hitoshi Yonezu at 10:00
| Comments(0) | 7つの習慣
2010年03月08日
本当に効果的に人生を営む人というのは、自分のものの見方の限界を認め、ほかの人のパラダイムと考え方に接することによって得られる、豊かな資源を活用する謙虚さを持っている人である。そういう人が相違点を尊ぶのは、その相違点こそが、自分の知識と現実に対する理解を増すものだと認識しているからである。自分の経験だけでは慢性的にデータ不足になってしまう、と知っているからである。
スティーブン・R・コヴィー著 『7つの習慣』より引用
私の若いころは変な強がりをしていて、あまり人の言うことを聞かなかったと思います。
自分に自信がなかったので、逆に強がっていました。
その後、いろいろな経験を積んできましたが、いまでも自信はなくて、反省、反省、の毎日です。
いまでは、自分の力が限られているということを痛切に感じ、人の力を借りなくては何も出来ない、とようやくわかってきました。
コヴィー博士のおっしゃるように、周りの方々は自分にないものを持っておられるのですから、豊かな資源です。
少々摩擦があっても、自分と違うからありがたいと感謝し、謙虚にお話を伺いたいと思います。

参考文献:『7つの習慣』 スティーブン・R・コヴィー (キングベアー出版)
Hitoshi Yonezu at 10:00
| Comments(0) | 7つの習慣

