2012年10月04日
今朝は久しぶりに参リンゴジュースを作って飲みました。10日ぶりくらいでしょうか。
レシピは人参とリンゴとレモンとショウガをジューサーにかけるだけです。頂いた梨も入れてみました。
人参リンゴジュースは私の日課としているものですが、今年は春くらいからいろいろなことがあり、外泊が増え、生活のリズムが崩れてしまって、人参リンゴジュースを飲めない日のほうが多くなっていました。
健康診断の血液検査の結果も、すべて定められた正常範囲内ではありますが、前年よりは少し悪くなっていました。
先日、同じ年の友人から言われた「リアル中年」という言葉が、いつまでも頭の中を響いています。つまりそういうことなのでしょう。
これからはもっと健康に注意していかなくてはいけないと思います。
貝原益軒はほどほどにせよということを繰り返し述べています。
す(好)ける物にあひ、うゑたる時にあたり、味すぐれて珍味なる食にあひ、其品おほく前につらなるとも、よほどのかぎりの外は、かたくつつしみて其節にすぐすべからず。
『養生訓』巻第三より引用
いつも葛藤することは、ここでやめておこうという気持ちと、もう今しか体験できないからやってみようという気持ちです。
私の場合は、ほぼ間違いなく、やってみようの気持ちが勝ちます。
目の前のおもしろそうな体験をすべてやってみようと思ったら、普段は相当節制しておかなくてはいけないわけです。
年を取るにしたがって基礎代謝が落ちていくのですからね。
今朝は人参リンゴジュースのおかげで気持ちがよいです。


『養生訓・和俗童子訓』 貝原益軒 (岩波文庫)
Hitoshi Yonezu at 10:00
| 健康
2012年08月06日
懐かしい友人と再会する夏。
親しい友人との宴会は楽しくてついつい飲み過ぎてしまいます。
貝原益軒の『養生訓』より引用します。
交友と同じく食する時、美饌にむかへば食過やすし。飲食十分に満足するは禍の基なり。花は半開に見、酒は微酔にのむといへるが如くすべし。興に乗じて戒を忘れるべからず。欲を恣(ほしいまま)にすれば禍となる。楽の極まれるは悲の基なり。
『養生訓』巻第三より引用
『養生訓』は、正徳三年(1713年)といいますから、いまからおよそ300年前に出版されました。
益軒が300年前に注意していることは、いま言われていることとほとんど変わりませんね。
「花は半開に見、酒は微酔に」
何事もあともう少しというところ、腹八分目で止めておかねばなりません。
「欲をほしいままにすれば禍となる。楽の極まれるは悲しみの基である。」
昔は現代のような治療法がありませんでしたから、病気は死と直面していたのだと思います。
できる限り長く健康でいられるように、自分を律していきたいことです。

『養生訓・和俗童子訓』 貝原益軒 (岩波文庫)
Hitoshi Yonezu at 10:00
| 健康
2010年08月07日
夏は、発生の気いよいよさかんにして、汗もれ、人の肌膚(キフ)、大に開く故、外邪、入やすし。涼風に久しくあたるべからず。沐浴の後、風にあたるべからず。且(カツ)夏は伏陰(フクイン)とて、陰気かくれて腹中にある故、食物の消化する事おそし。多く飲食すべからず。温なる物を食(クラ)ひて、脾胃をあたたむべし。冷水を飲むべからず。すべて生冷の物をいむ。冷麺、多く食ふべからず。
『養生訓』巻第六より引用
シャワーを浴びたら、クーラーか扇風機にあたっていないと、どうしても暑さが収まりません・・・
そして、毎日毎日、そうめんばかり食べていますが・・・
貝原先生は、冷たい風にあたり続けるのはよくないし、冷たいものばかりを食べるのもよくないとおっしゃっています。特に冷たい麺には気をつけろと。
子どもの頃、親からよく言われてきたこととまったく同じようなことですが、江戸時代から伝えられてきた生活の知恵なんですね。
もう皆さまは夏休みでございましょうか・・・疲れは夏の終わりにどさっと来るかもしれません。どうか冷たいものにお気をつけあそばせ。

『養生訓・和俗童子訓』 貝原益軒 (岩波文庫)
私の手元にある岩波文庫の『養生訓・和俗童子訓』は、「1990年5月25日 第33刷発行」の約20年前のものですが、価格は520円(本体505円)です。
いまは何刷までいっているのかわかりませんが、アマゾンによりますと、同じ本の価格が735円(本体700円)になっています。
ほぼずっとデフレ状態だったといってよいこの20年ですが、規制されている商品の価格は確実に上がっていますね・・・
Hitoshi Yonezu at 10:00
| 健康
2010年04月20日
わかき時より、老いにいたるまで、元気を惜しむべし。年わかく康健(こうけん)なる時よりはやく養ふべし。つよきを頼みて、元気を用過すべからず。わかき時元気をおしまずして、老て衰へ、身よはくなりて、初めて保養するは、たとへば財多く富める時、おごりて財をついやし、貧窮になりて財ともしき故、初めて倹約を行ふが如し。行はざるにまされども、おそくして其しるしすくなし。
貝原益軒『養生訓 巻第二 総論下』より引用
若いときに、健康だからといって、元気に活動しすぎるのはよくない。若いときから元気を養うべきだ。若いときにがんばりすぎてしまうのは、お金があるときに贅沢をつくし、貧乏になってからやっと倹約を始めるようなものだ。
「若いときに無理しすぎて・・・」「20代のころお酒を飲み過ぎて・・・」とおっしゃる方がよくおられます。若いときは、あまり疲れることもなく、回復も早いから、ついつい無理をしてしまいます。
貝原益軒は、うまいことを言ったものです。元気をお金のようなものだというなら、お金のあるときに浪費をしてしまうように、若いときに元気を使いつくしてしまうのは、良くないことだなあと理解することができます。
江戸時代の本草学者が言っていることですから、現代医学からみて科学的根拠があるかといえば、ないといえましょう。
しかし、健康については、人によって千差万別ですから、科学的な答えがあるわけではありません。それぞれの方が自分にあう健康法を実践されています。
養生訓は江戸時代から歴史の流れに耐えて読み継がれていますから、日本人の健康にあう何かが書かれているのだろうと思います。
古文ですが、素養のない私でもだいたいの意味は分かりました。皆さまもご参考になさってください。

参考文献:『養生訓・和俗童子訓』 貝原益軒 (岩波文庫)
Hitoshi Yonezu at 10:00
| Comments(0) | 健康
2010年01月10日
メタボという言葉があまねく使われる昨今、腹八分目がよいと言いますが・・・
江戸時代にもすでに同じことが言われていたのです。
貝原益軒の『養生訓』は、正徳二年(1712)に書かれた生活の心得書です。「巻第三 飲食 上」より引用いたします。
珍美の食に対すとも、八九分にてやむべし。十分に飽き満るは後の禍あり。少(すこし)の間、欲をこらゆれば後の禍なし。少(すこし)のみくひて味のよきをしれば、多くのみくひて、あきみちたるに其楽(たのしみ)同じく、且(かつ)後の災なし。万の事十分にいたれば、必(ず)わざはひとなる。飲食尤(もっとも)満意をいむべし。又、初に慎めば必(ず)後の禍なし。
(以上引用)
以下は私訳です。
珍しいもの、おいしそうなものがあっても、腹八分か九分でやめておきなさい。満腹になるまで食べるとあとで病気になりますよ。少しだけ欲を抑えることができればいいのです。少しだけ食べて味のよさを知ることができれば、たくさん飲み食いするのと同じくらいの楽しみを得ることができますし、あとからも何の問題もありません。何であってもたくさん食べれば、必ずあとで大変なことになります。満腹になるまで食べてはいけません。はじめから慎んでくださいね。
(でたらめに現代語訳をしましたが、古文の先生、こんな感じでよいでしょうか・・・)
江戸時代のことですから、いまのようにいろいろな食べ物はなかったと思うのですが、それでもお腹いっぱい食べたくなるような魅力的なものがあったのでしょう。何を食べていたのかなーと想像してしまいます。
私の父母や、亡くなった祖父母に聞いた話では、60~70年前、戦前戦後の日本には、食べるものがありませんでした。
腹八分目、当たり前のことだったでしょう。
私の子供のころは、親が忙しくてご飯が作れなかったということはあったかもしれませんが、後から食べられたわけで、食べるものが不足していたという記憶はありません。
今の日本では、食べるものは、量も質も種類も、すべて満たされています。
食べるものは確実にあることが前提で、うまいか、まずいかを議論するような時代になりました。だから、メタボの問題や、腹八分目という話が出てきているのでしょうが・・・
貝原益軒が『養生訓』を書いたのは、前には徳川吉宗、後には徳川家治、田沼意次の政治、と流れていく、江戸幕府第九代将軍、徳川家重の時代です。
腹八分目が説かれていたくらいですから、いまと同じように、このころも平和な世の中だったのでしょうね。

参考文献:『養生訓・和俗童子訓』 貝原益軒 (岩波文庫)
Hitoshi Yonezu at 11:27
| Comments(0) | 健康
2009年09月28日
昨日は東御市で長野県東信地区のロータリークラブの勉強会(IM、会員セミナー)がありました。
記念講演として、東京大学教育学部長の武藤芳照先生が、「転ばぬ先の杖と知恵 転倒・骨折・寝たきりにならないために」という題目でお話をしてくださいました。
武藤先生は東御市の「ケアポートみまき」の中にある身体教育医学研究所の活動を通じて、昔からこの地区とはご縁があるのだそうです。
先生は身体教育学の教授ですが、そもそも整形外科の医師で、オリンピック水泳チームのチームドクターをなさった方でもあり、健康にかかわるいろいろなお話を伺うことが出来ました。
高齢者の方が転倒、骨折をされて、治療をしているうちに、だんだんと身体が弱ってきたという話をよく聞きますが、実はそれは間違いだそうです。
転倒をするということは、それだけ体が弱っていたということだそうです。つまり、転倒は原因ではなくて、結果だというのです。
転倒をしないようにするには、若いうちから筋力増強をしておいた方がよいようです。
運動不足の私としては、耳の痛い話でした。
また、今でも、「運動中には水を飲まない」という誤った常識がまかり通り、学校などで運動中の生徒が熱中症で亡くなるケースがあるそうです。
私も大学時代、ワンダーフォーゲル部で登山をしていた時、水を飲まないことが偉いことと思われていて、それを競い合っていたようなことがありましたが、今考えると、大きな間違いでした。
水の摂取は全般的に不足気味で、平均的にはコップであと2杯の水を飲めば、一日に必要な水の量を確保できるそうです。
私は、毎日ペットボトルのミネラルウォーターを買って飲んでいます。水を飲んでいるとお茶やコーヒーはあまり飲みたくなくなります。
いずれにしても、健康が人生の基礎ですから、健康ないまこそ意識して気をつけようと思いました。
よいお話を聞けてよかったです。
人気ブログランキングへの投票リンクです。私のブログが皆さまのお役に立てましたら、クリックをお願い致します。
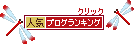
Hitoshi Yonezu at 10:00
| 健康
2009年07月06日
りんご、人参、しょうが、レモン・・・ジューサーでつくる私の朝の自家製ジュースの原材料です。
「朝食は自家製ジュースだけです。」というと、みなさんがびっくりされます。
中には朝食をとらないことはよくないことだと注意してくださる方もおられます。
私にとっては、もう五年近く続いている習慣です。今のところ、ですが、健康診断の数値はすべて正常で、体の調子はとてもよいです。
ジュースを始める元になった考え方はいくつかあるのですが、中でも一番分かりやすいのが、石原結實先生の考え方です。石原先生はもう何十冊も本を書かれています。どの本も内容は似ているので、どれか一冊を読まれれば、先生の考え方がよくわかります。
現代人は食べすぎだというのが石原先生の説ですが、確かにジュースを始めるまでの私も食べすぎでした。その頃に比べると、今はとても楽です。
興味のある方はご参考になさってください。
参考文献:『空腹力』石原結實(PHP新書)
『男を持続させる食べ物、生き方』石原結實(ベスト新書)
参考:『朝食は野菜ジュース』
http://highlyeffective.naganoblog.jp/e140766.html
Hitoshi Yonezu at 18:45
| Comments(0) | 健康
2009年04月02日
『100歳まで元気に生きる!』は、元気に長生きする秘訣を、食べ物や運動、精神面などから総合的に説いた書籍である。著者はアメリカ人で、サーティーワンアイスクリームの創業者を父にもつ。アイスクリームを製造する父に対して、健康的な生活を志す著者は反発し、一時は仲たがいをした。しかし、父が健康を害したことなどもあり、最終的には分かり合うことができたという。
世界の長寿の地域がいくつか挙げられているが、その一つとして、沖縄について詳しい解説がなされている。
また、世界一の長寿国として日本の分析もなされている。日本は世界の裕福な国の中で、経済的にもっとも平等であるから、健康を維持できたのだという。人々が他人を信用し、相互の利益のために協力する社会は、誰もがまあまあの分け前を得ることができる。逆に富裕層と貧困層の格差が大きいほど国民の健康状態は悪くなるそうだ。
この本は2006年に書かれているが、著作のために調査をしたのはさらに前のことだろう。現在の日本はどうだろう。経済的に平等といえるのか、だから国民はみな健康だといえるのか、人々の信用関係は維持できているのか。いま状況は少々変わってしまったのではないか。
後半部分には愛や精神面の大切さが書かれている。その中の「死は敵ではない」という節にすばらしい文章があるので引用する。
(以下引用)
「見た目を最高にしたいと望むのは悪いことではないが、加齢のプロセスと戦っているのならば、あなたの負けは目に見えている。年をとらないふりをしている人は、自分が死をともなう勝ち目のないレースをしていることをいつか思い知らされるのだ。
ほんとうに重要なことは髪の毛を染めるかどうか、しわ取り治療をするかどうかではない。あなたが加齢のしるしを含めた人生の経験を軽蔑するのではなく、愛情と是認を持って歓迎するかどうかなのだ。人生のすべてのステージは、固有の才能と力を持っている。もっとも重要なことは、人生を通して、あなたの内面の美しさを輝かせることなのだ。」
(以上引用)
映画やテレビドラマの役柄などを通じて、素敵なひとだな~かわいいな~と、憧れた女優さんがいた。その彼女がトーク番組に出たときに、「ええっー!」と驚いてしまったことがある。
話しているのを聞いて、「こんな考え方をしている人だったの~こういうこと言う人だったの~」と、がっかりしてしまったのだ。
役の中では美しかった。でも、それは一つの姿にすぎなかったのだ。別の面から見たら、私の想っていた女性とは大きくかけ離れていた。人間が磨かれていなかったことが残念だった。
セリフではない何気ない会話では、内面が出てきてしまう。外見の美しさだけで繕おうとしても、早晩ばれてしまう。
どこそこの女優が好きだという人に、私もそういうことがよくあり、それはそれで私は全く同感するが、その女優と実際に友達になったときに、本当に好きだといえるのか、そこでようやく判断できるはずだ。実際には友達にはなれないから、話を聞いたりするしかないのだが。
世の中にはすべてフィルターがかかっている。見かけだけで判断できるはずがない。
もちろん、誰とは言わないが、内面が美しい女優さんはたくさんおられる。年の経過とともに顔つきが変わって、存在感を増していくのだ。私はそういう女優に惹かれる。
この本に書いてあるのだが、我々の文化は死を失敗としてとらえようとしている。
しかし、死を失敗だというならば、死に向かって毎日、瞬間瞬間を生きている我々のこの存在自体が失敗ということになる。
死も老化も失敗ではない。
自分が生きていく、成長していく、その過程を楽しめるようになりたいものだ。
参考文献:『100歳まで元気に生きる!』ジョン・ロビンズ(アスペクト)
この書籍は前半は栄養の話等が続いて少々退屈ですが、後半にいけばいくほど面白くなります。ぜひご一読ください。
昨年8月のこのブログでも同じようなことを書いてしまいました。恐縮です。
http://highlyeffective.naganoblog.jp/e139228.html
Hitoshi Yonezu at 13:14
| Comments(0) | 健康
2008年08月27日
毎朝、ジューサーでジュースをつくっている。必ず入れているものはりんご、人参、レモン、しょうがである。朝食はそのジュースだけである。出張していたり、起きることが出来ないくらいの二日酔い(滅多にないが)でない限り、欠かすことのない習慣である。
日記を読み返してみたら、朝食を自家製ジュースに切り替えたのは2004年11月28日だった。もう4年近く続けていることになる。その前日まで、私の朝食はフルーツだった。その季節のいろいろなフルーツを食べていた。よく食べたフルーツはオレンジ、パイナップル、スイカ、桃、メロン、ぶどう、梨、柿、りんごなどである。
フルーツだけの朝食はその年の3月頃から始めたはずだと思うのだが、日記には記録がなかった。フルーツだけの朝食も人から見れば変わっていると思われるだろうが、それは胃痛を治すために始めた事だった。私は職業柄、社内で急に料理の味見を頼まれたり、視察のために一日に何度も外食をしなくてはいけなかったり、お客様とのお付き合いで、二次会三次会とはしごをしなくてはならなかったり、とにかく食べすぎ飲みすぎだったのである。
食べすぎ飲みすぎということは胃を酷使しているということであり、それが胃痛の原因になっていたと思う。本当は、一食抜いて何も食べなければ胃を休めることになるのだが、そうするとその足りない分を、一日のどこかで補充してしまうだろう。せめて朝だけは胃に負担の少ないフルーツにしようと思ったのである。(なぜフルーツが胃にやさしいかの説明は長くなるので、また別の機会に)
フルーツが胃にやさしいなら、ジュースはフルーツや野菜を小さく砕いているのだからもっと胃にやさしいはずである。りんごと人参でつくった生ジュースが特に体によいという話は以前から知っており、やってみようと思ってはいたのだが、ジューサーでジュースをつくるということの踏ん切りがつかなかった。ジュースにするということは、残菜が多量に出るわけで、最終的にはそれを捨てることになる。それがもったいなくて、贅沢なことのような気がしていたのである。特に亡妻がそう感じていたようだった。だから、生ジュースをつくることは申し訳なくて出来なかったのだ。
私としては、病気の妻に対してよいことをしてあげるなら残菜が出ようがかまわないだろうという思いがあったし、フルーツの種類によっては体が冷えるということが自分の体験で分かってきた。そこで、ようやく自家製生ジュースをつくろうと決心したのである。妻はしばらくの間、人参の残菜を使って人参ケーキをつくってくれた。それはそれでとてもおいしかった。しかし、毎日大量に出来る人参ケーキをすべて食べきることは出来なかった。そのうちに自家製の生ジュースの素晴らしさが分かるようになると、残菜の無駄はあまり感じなくなってきた。私は胃痛も冷えもなくなり、快調になった。妻も病に効きそうだと喜んで飲んでいた。
この4年間の間に、生活は夫婦二人暮らしから、男一人暮らしに変わったが、最初から自分でつくっているので、つくるということでは何の変化もない。二人分を作っていたときの量は変えずに、少量だが仏前の分は別にとって、残りは一人で全て飲んでいる。
実は毎朝約1リットルのジュースを作っているのである。素材は出来る限り新鮮なものを、手に入るなら有機や無農薬のものを選んでいる。例えば昨日の朝(今朝は大阪出張中)は、人参3本、りんご3個、レモン1個、しょうが少々の基本に加え、ゴーヤを3分の1と、青梗菜を5葉を加えた。これで約一リットルになる。雑食で大食いの私にとってただ一つの健康食である。
Hitoshi Yonezu at 07:16
| Comments(0) | 健康



