2010年01月27日
瓜田に履を納れず李下に冠を正さず
(かでんにくつをいれずりかにかんむりをたださず)
瓜畑で履き物を履き直そうとかがめば、瓜を盗んでいるのではないか疑われ、李(すもも)の木の下で冠をかぶりなおせば、李を盗むのではないかと疑われかねない。人から疑われるようなまぎらわしいおこないは避けようということ。
仕事でも日常生活でも熱心に活動していると、自分でも気づかないままに、瓜畑や李の木の下に迷い込んでしまうことがあるものです。
自分が何をしたか、がもっとも重要ですけれども、人がどう見ているか、ということも、軽視するわけにはいかないのですね。
最近では痴漢の冤罪事件もいくつか起こったせいか、都会の満員電車では、両手で吊皮を握りしめている人がいるという笑うに笑えない話も聞きます。
ブログも、匿名で書かれている方は問題ないでしょうが、私のように本名を明かしている場合には、文章によって、私になんらかのイメージがついてしまっているのだろうな~と思います。
私のブログを読んでくださっていた初対面のお客さまとお話を致しましすと、自分では思いもかけないようなことを言われることもあります。
「君子危うきに近寄らず」という成句もあります。
今年は虎年だから、「虎穴に入らずんば虎児を得ず」だ!と考えていましたが・・・
バランスが大切ですね・・・

関連した私のブログ:『新年のご挨拶』
http://highlyeffective.naganoblog.jp/e374185.html
Hitoshi Yonezu at 10:00
| Comments(2) | 日常生活
2010年01月20日

小泉元総理大臣のお話を伺う機会に恵まれました。
虎年の新年を迎え、長岡藩の小林虎三郎の米百俵の精神と、吉田松陰(幼名:虎之助)の辞世の句を教えていただきました。
いずれも佐久間象山の門下で、「象門の二虎」と称せられています。
小泉元総理が2001年の所信表明演説で、小林虎三郎の米百俵の精神を引用されたことは余りにも有名です。
吉田松陰の辞世の句を読むと、松陰がいかに強い思いをもって行動を起こしていたのか、伝わってきます。
親思ふこころに勝る親心 けふの音づれ何ときくらむ
身はたとひ武蔵野の野に朽ちぬとも留め置かまし大和魂
日本はまだまだいけるぞ、強い精神で自信をもって前進しよう、と思った夜でした。

Hitoshi Yonezu at 10:00
| Comments(0) | 日常生活
2010年01月08日
昨日の社内会議では、個人の能力、行動81項目について、自己評価と上司からの評価を出してもらい、比較、確認をする作業をしました。
例えば、次のような項目にイエスかノーで答えるのです。すべて否定の内容ですので、イエスと答えたものは問題がある項目です。
仕事に自信が持てない。
都合のいいことしか報告しない。
自己管理がまるで駄目だ。
率先垂範をせず、ただ言うだけ。
スケジュール作りが下手だ。
部下のしつけが出来ない。
部下にやさしすぎる。
本を全然読んでいない。
明らかな自分の非を素直に認めない。
・・・
・・・
それぞれの自己評価を見てみると、私から見て感じることとそんなに離れてはおらず、自分のことはおおよそ認識しているようでした。
しかし、中には自分の悪い習慣を自分では全く気付いていない部分もありました。周りで働く人たちはみんなそのことに気が付いているのです。
そのことを本人に伝えるのは、本人にとっては厳しい場面ですが、長い人生を思えば、率直に言ってあげなくてはいけません。
会議でこれを行うと、私が一人だけがそう思っているのではなく、周りのみんながそう思っているのだと全員で伝えることが出来るので、本人に対する影響力も大きいです。
私は、一項目だけですが、「困ったなあ」を連発する、という項目にイエスと入れざるを得ませんでした。
スケジュールが詰まっている時に、トラブルが起こると、無意識に「困ったなあ」と言っておりました。
私は社長ですので、お客さまに叱られることはありますが、社内では注意してくれる人はいないのです。せいぜい友人や、辛口の女性から、「米津さんは○○ですね」と言われるくらいのものです。
それだけに、社長には高い自己管理能力や自律性が求められるのです。
『ドラッカー 365の金言』の1月8日の節より引用します。
知識労働者には自律性が必要であるからこそ、彼らに対し、なすべきこと、もたらすべきものを明らかにすることを要求しなければならない。
(中略)
知識労働者たる者は、自らの行動計画を組織に提示しなければならない。何に重点をおくか、いかなる成果を期待できるか、それはいつまでに可能か。知識労働者には自律性と責任がともなう。
(以上引用)
難しい分析をする人、難しい書類をつくっている人、難しい資格をもっている人、有名大学を出て大企業に勤めている人・・・などのことを知識労働者というのではありません。
どのような職業、職務であれ、仕事を通じて自分で情報を集め、それを自分で分析し、自分の仕事に活用して、効率化や範囲の拡大ににつなげていくことが出来る人が知識労働者です。
社員たちには、高い自律性をもって、知識労働者になってほしいと思いました。

参考文献:『ドラッカー 365の金言』 P.F.ドラッカー (ダイヤモンド社)
Hitoshi Yonezu at 10:41
| Comments(0) | 日常生活
2010年01月07日

昨日は上田商工会議所の賀詞交換会、一昨日は上田三田会の新年総会が開催され、この後もいろいろな新年会が目白押しです。
私はできる限り多くの新年会に参加させて頂き、皆さま方に昨年の御礼と新年の御挨拶を申し上げております。
表向きのお話を伺っておりますと、景気はほぼ底を打ち、今後は上向きになっていくという明るいコメントがほとんどです。
しかし、中小企業の社長さまに個別にお話をしてみると、今年一年をどちらかといえば悲観的に見ておられる方が多いです。
私のように経済の末端で商売をしているような者には、経済を引っ張っていくような力があるはずもなく、何もできません。
ただし、知恵を絞り、一生懸命に自分の仕事をすることはできるのです。
お客さまの求める場を創造し、より高いレベルでお客さまの目的を果たし、お客さまがご本業で御活躍されることにつなげていかねばなりません。
「もう最近は宴会もできなくなっちゃったよ。ごめんね。」とわざわざ声をかけてくださった社長もおられ、本当に恐縮してしまいました。
どんな状況であれ、周りのせいにするのではなく、まだ自分の力が足りないんだと反省しようと思いました。

Hitoshi Yonezu at 11:12
| Comments(0) | 日常生活
2009年12月31日

ささやでは、今朝6時からおせち料理づくりに大忙しです。
写真は、出来上がってきたおせち料理を風呂敷で包装しているところです。
今年も、いろいろなことがありました。ブログには書けなかったこともたくさんありました。(ここに書かなかったことの方が多いですね・・・)
今年に限らず、毎年いろいろなことがあります。そういうことを乗り越えていくことが、人生の試練なのだなあと思います。
何があったにせよ、こうやってブログを書いていられる今の幸せを感じたいと思います。
皆さまのおかげでございます。一年間大変お世話になりました。
心より厚く御礼申し上げます。
誠にありがとうございました。
来年もご指導、ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願いいたします。
どうぞよいお年をお迎えください。

Hitoshi Yonezu at 11:37
| Comments(2) | 日常生活
2009年12月29日
昨日は、仕事納めの企業や団体も多く、当社の各店舗でも、たくさんのお客様が忘年会やご宴会をしてくださいました。
誠にありがとうございました。
中学校の柔道部の顧問だったK先生が、ある学校の忘年会のためにうちのお店に来ておられ、十数年ぶりにお会いすることが出来ました。
少し小さくなられたように思いましたが、お話をすると、昔と何もお変わりなく、お元気そうでした。
先生はクラスの担任ではなく、柔道と理科を教えてもらっただけですが、私にとっては中学の多感な時期に、人生を教えてくださった本当に尊敬できる方です。
武士のような、ぶれない生き方を教えくださった先生です。
お会いするたびに、先生に教わったことがいま私の人生の土台になっていますという感謝の気持ちをお伝えたしたいと思うのですが、先生はあまりおしゃべりされませんし、謙虚であっさりした性格でいらっしゃるので、どうも上手にお伝えすることができません。
中学生のころ、男はべらべらしゃべるもんじゃない、とよくおっしゃっていたので、少しは分かってくださっているかな~と思います。
私自身がもっと成長し、成果を出すことが、先生に恩返しすることだろうな~と考えておりました。

Hitoshi Yonezu at 11:29
| Comments(0) | 日常生活
2009年12月25日
書評欄で『快適「自転車生活」入門』という本を見つけ、楽しそうだな~私にはない世界だな~やってみようかな~と思って、すぐに買ってしまった。
「ロードバイク」という自転車を楽しむための入門書である。
ナガブロの人気ブロガーのなかにもロードバイクを楽しんでおられる方がいて、ツーリングの様子を報告してくださっている。
この本を読みながら、中学生のころ、親に買ってもらった、なんてことはない、ただの「サイクリング車」で、上田から軽井沢まで一人で「サイクリング」に行ったことを思い出した。
そのときは自転車に乗って、どこまでいけるか挑戦してみたかったんだ。上田から軽井沢まで往復で70キロ近くあるのではないだろうか。中学生の冒険だ。
柔道部主将で体力に自信のあった私だったが、夕方へとへとになって帰ってきた。でもそのワクワクするような思い出は忘れない。
某大学陸上部の記録保持者で、いまだにトレーニングに励んでいる高校の同期生に、
「おれ、ロードバイクやってみたいんだけど、どうかな~」
と相談してみた。
「なーに、言ってんだ!あれはすごく大変なんだぞ。いきなりは無理だ。まずはジムで体を鍛えてからだ!おれの通っているジムに来い!」
と言われてしまった。
そりゃ、そうだよな~私のいまの体力ではな・・・夢が泡と・・・
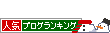
参考文献:『快適「自転車生活」入門』 中野隆 (アスキー新書)
Hitoshi Yonezu at 10:00
| Comments(7) | 日常生活
2009年12月17日

昨日は、お客さまにご一緒して、日本酒の会に参加してきました。
写真は、鳥取県の諏訪酒造の冨田と、滋賀県の畑酒造の大治郎です。
冨田は黄色を帯びたお酒で、お燗にすると、まるで赤ワインのような複雑な香りがしました。のど越しも複雑ですので、肉料理や味の強いお料理にも合うと思いました。常温で飲むと、特徴が抑えられ、全く別の味になっていました。
少し変わった、ツウ好みの日本酒ですが、ワイン好きな方でしたら、このお酒が好きになることでしょう。
大治郎は純米吟醸で、米米しいふくよかな感じがしました。きつくないやわらかい感じで、これだけでいくらでも飲めてしまいそうでした。
鮟鱇鍋のだしで作った薄味の雑炊が美味しくて、三杯も食べてしまいました。
このところ太り気味ですが、師走ですから・・・
・・・しばらくこのままでお許しください・・・
ご一緒した皆さまと楽しい時を過ごしながら、師走の夜が更けていきました。

Hitoshi Yonezu at 15:46
| 日常生活
2009年12月16日
先日、お客さまと、ある建物が傾いていたということについてお話ししていたとき、私はいつも使っている言葉で、
「あの建物は昔、かしがっていたんですよ。」
と申し上げました。
すると、お客様が、
「かしがるって、長野の方言じゃないですか?うちの地方では、かたがる、って言いますよ~」
とニコニコしながらおっしゃるのです。
そう言われてみれば、「かしがる」という言葉は、なんとなくおかしいなと思いました。
日本語を大切にしたいと宣言した私としては、変な日本語を使っていると気持ちが悪いので、さっそく辞書を調べてみました。
参考ブログ:「『日本語教のすすめ』を読んで」
http://highlyeffective.naganoblog.jp/e364008.html
広辞苑を見ると、傾くことに関する動詞で以下のものがありました。
傾く(かたむく) 自五、他下二
傾ける(かたむける) 他下一
傾ぐ(かしぐ) 自五
傾げる(かしげる) 他下一
傾ぐ(かたぐ) 自四、他下二
傾げる(かたげる) 他下一
中学のときに習った動詞の活用を忘れてしまって、正しいことが分からないのですが、これを見るかぎり、「かしがった」も「かたがった」も、どちらも国語的にはおかしいような気がします。
傾ぐ(かしぐ)の「自五」活用、傾ぐ(かたぐ)の「自四」活用は、どうなるのですかね・・・
それとも、お客様が指摘してくださったように、方言なのでしょうか。
どなたか、正解を教えてくださいな~。

Hitoshi Yonezu at 15:18
| 日常生活
2009年12月06日
研修旅行で韓国のソウルに来ております。今日は北朝鮮との国境の非武装地帯(DMZ)を見学してまいりました。韓国のみなさまは、我々日本人の前では言いずらいことも含めて、さまざまな深い想いをもっておられます。日本は平和な国であるということを強く感じました。この状態に感謝をして、いま自分にできることはどんどん進めていこうと思いました。
Hitoshi Yonezu at 19:48
| 日常生活
2009年12月03日

RCのお客さまと、二か月毎に開催している「ワインを楽しむ会」が昨夜ささやにて開かれました。
今回はフランスのブルゴーニュ地方のワインを飲みました。
I 社長の卓越したセレクションで、変化の少ないブルゴーニュワインに、はっきりとした段階がつき、一種類ずつ飲む度に、確実にステップが上がっていきました。
同じワインでも、飲む順番によって全く違う印象になりますので、選び方やお料理との合わせ方に、選ぶ人の技量が発揮されます。(だからソムリエという仕事があるのですね。)
昨夜のワインリスト
1.ドメーヌ ランドロン ミュスカデ プリムール 2009
2.レゼルバ ベルトミュー シャルドネ 2008
3.ドメーヌ クロ マリ 2007
4.マルサネ ドメーヌ ピエール ラヴナン 2002
5.ドメーヌ ルクロワジー コート・ドゥ・ニュイ・ヴィラージュ
6.コトー・デュ・ラングドック・ピク・サン・ルー・オリッヴィエット・ルージュ 2007
ささやのフレンチメニュー
鮪と帆立とずわい蟹のタルタル仕立て
キッシュ・ロ・レーヌと榛名地鶏のスモーク ディジョンマスタード添え
根菜とあさりのフリット
金目鯛と芝海老のファルス ヴァンブランソース
鹿肉ロースのポワレ フランボワーズソース
バナナのティラミス
コーヒー
パン
21人のお客様で19本のワインが空きました。私は2番と6番のワインが好きになりました。
楽しい夜が更けていきました。今日からまた一生懸命仕事ができそうです。
みなさまありがとうございます。

Hitoshi Yonezu at 10:00
| 日常生活
2009年12月01日
品書きに鰤書き足して鰹消す 鈴木真砂女
毎年のことですが、もう師走なのですね。
毎日お忙しいこととは存じますが、皆さまがお元気で、よい12月をお過ごしくださいますことを、心よりお祈り申し上げます。

Hitoshi Yonezu at 10:02
| 日常生活
2009年11月22日
年をとるたびに、身体や脳の機能は衰えているのかもしれませんが・・・
単に衰えていくのではなく、衰えながらも、鍛錬され、強いしなりのようなものが醸造されるような感じを覚えることがあります。
体力では20歳代のころに完全に負けているでしょうが、体調はいまのほうがよいですし、長く歩くことも楽しく感じます。精神的にも、何か重いものが取れた感じがして、いまのほうが楽ですし、安定しています。
脳がさえていたはずの20歳代に、読もうとしても読めなかったり、読もうという気が起こらなかった本を、いまでは読むことが出来ます。
歴史は学べば学ぶほど、人間を豊かにさせてくれますが、人間の一生も歴史のようなもので、年をとるたびに、何らかの積み重ねがあるのだろうと思います。
昔からどこの国でも、長老を大切にし、何か問題が起こると、まずは長老に相談するというのも、長い間に積み重ねた知恵が、人から信頼され、問題解決に有効だからだと思います。
私の父母は幸いにして元気ですので、何を言うか大体わかってはいるし、私の意見とは全く逆のことや、非現実的なこと、昔のことを言うこともありますが、長老の意見として、一応、聞くだけは聞いてみることにしております。
よい年の取り方をしていくためには、自分自身によい種をまいて、太陽の光を燦々と降り注ぎ、よい水をあげて、豊かな畑を育てていくことではないでしょうか。
周りの人を喜ばせ、お役に立てるような思考や行動をしていきたいと思います。

Hitoshi Yonezu at 11:38
| 日常生活
2009年11月14日
最近、東京では立ち飲みのお店が相当増えて、お客さまもかなり入っています。一時の流行りではなく、一つの遊び方として定着していくのかもしれないと思います。
信州にも立ち飲みのお店がぼつぼつ出てきています。立っては飲むのはどうか?短時間といえども座ってゆっくり飲みたい、という方もいます。
しかし、立って飲んでも意外と疲れないし、仲間と短時間で楽しいコミュニケーションがとれ、価格も安い、というメリットもあります。
話は少し変わりますが、東京で業界団体の会合や異業種交流会、勉強会などがあると、懇親会はほぼ間違いなく、立食形式のパーティーです。その場合、基本的にパーティー会場には座れる場所はありません。
婚礼などのフォーマルな式典でない限り、着席形式のパーティーはほとんどないと言えます。
立食の場合、好きな場所に自由に移動出来て、コミュニケーションをとりやすいということ、好きな料理を好きなだけ食べられること、帰るときにはさっとあがれること、などのメリットがあるのだと思います。
信州ではどんな懇親会でも着席が主流で、立食についてはまだ理解が低いのが現状です。また、ご年配のお客様が多い場合は、着席のパーティーのほうが親切です。
私の子供のころは、立ったまま飲み食いするのは、品が無いことだと親から聞かされていました。
最近では欧米化が進んできて、そんなことも言われなくなりましたね・・・

Hitoshi Yonezu at 11:22
| 日常生活
2009年11月13日
東京へ経営の研修に来ております。
昨日の研修で、自社の商品を分類して、それぞれの売上高を算出し、PPM(プロダクツポートフォリオマネジメント)のマトリクスに当てはめてみるという作業をしました。
PPMとは、成長性を縦軸、収益性を横軸にとったマトリクスで、商品を四つに分類して、それぞれの商品の成長のサイクルを分析するものです。負け犬、問題児、花形、金のなる木・・・という分類で有名ですね。
数年前にもこの分析をした記憶があるのですが、改めて分析してみて、新たな気づきがありました。経営者の方は一度お試しください。何か見えてくると思います。
22時ころ研修が終わりましたが、一日中ホテルにいたので、万歩計を見ると、なんと1,500歩しか歩いていませんでした。
いくら運動不足の私とはいえ、こんなに歩かないことはありません。
身体の危機を感じて、ホテルの外を30分ほど歩きました。
外は真っ暗です。
しかも、新興のマンションやビルが立ち並ぶ立地ですので、人影はまばらです。
私は黒っぽい普段着でしたので、変な人に間違えられないようにと思い、明るいところを選んで、女性が歩いているのを見つけると、出来る限り遠くへ離れて、すたすたと歩きました。
この界隈には相当数のもんじゃ焼き屋さんがありました。入りたかったのですが、カロリー消費のために歩いているのですから、我慢しました。
ホテルに戻ると6,000歩まで到達していました。最後に、ホテルの9階の部屋まで階段で上がりました。風の強い夜でした。
今日は研修最終日です。

Hitoshi Yonezu at 10:00
| 日常生活
2009年11月12日
東京なら、よくあることなのかどうか・・・
昨日、ある地下鉄の駅でのことです。
朝9時ころでしたが、地下鉄はまあまあ混んでいました。出勤時間帯ですので、列車内が混んでいるのは仕方ないと思うのです。
私は3泊の出張でしたので、キャスター付きバッグを持っていましたが、それほど問題なく移動できました。
ところが、です。
改札を出て、地上に上がろうとしたら・・・改札の外の通路全体が、行列になっているのです。 広い地下道の幅いっぱいに行列です。
地上に上がれない?
この駅ではよくあることのようで、録音された女性の声が、「この時間帯は通路が混みあいますので、順序よく並んでお進みください。」というようなことを、繰り返し繰り返し、放送していました。
通勤客の方々も当たり前のような顔をして並んでいました。
行列が一歩ずつ前へ進んでいきます。前に進んでみてわかったことは、地下鉄から地上に上がる階段が狭すぎて、隘路になっているのでした。
結局、地上に上がるのに10分近くかかりました。
東京で満員電車にはよく出くわしますが、「満員通路」は初めてでした。
出口を増やすか、階段を広くすればいいと思うのですが・・・このままで防災上、大丈夫なんでしょうかね・・・

Hitoshi Yonezu at 10:00
| 日常生活
2009年11月11日

ホテルの屋上から近くのマンションを撮影しました。実際に見ると宝石のようにきれいなビルなのですが・・・
東京は一日中雨が降っていました。今朝、地下鉄の駅からホテルまで7分ほど歩きましたら、スーツがびしょびしょになってしまいました。
今日から三日間、経営の研修のため、ホテルに缶詰めです。
夜遅いのに、みなさんまだ熱心に課題に取り組んでおられます。
この研修で学んだことは、必ず当社の経営に活かします。社員の人格を向上させるため厳しく教育し、お客様のお役に立てるようにしたいと思います。

Hitoshi Yonezu at 22:42
| 日常生活
2009年11月08日
昨日は上田ロータリークラブの創立50周年記念式典が、ささやにて行われました。私も末席ではありますが、会員の一人としてお手伝いを致しました。
上田RCは昭和34年11月12日に創立した、会員数59名を擁する奉仕団体です。
私は創立40周年の年に入会しましたので、会員歴は今年でちょうど10年となりました。
昨日の式典では、先輩方の想いをお聞きし、上田RCに在席された人々の歴史の重みを感じることが出来ました。
会社でも家族でもない、奉仕を目的として集まった社会人の集まりですが、上田RCの結束は固く、かといって肩に力の入っていない、よい集まりだと思います。
準備は朝8時から始まり、4次会が終わったら、午後9時半になっていました。楽しい一日でした。
御参考までに
ロータリークラブの四つのテスト 言行はこれに照らしてから
1.真実かどうか
2.みんなに公平か
3.好意と友情を深めるか
4.みんなのためになるかどうか
人気ブログランキングの投票サイトです。私のブログが御参考になりましたら、クリックをお願いいたします。

Hitoshi Yonezu at 10:02
| 日常生活
2009年11月06日

今朝、松本から上田へ移動する途中で撮影しました。三才山峠付近です。
10月27日時点の紅葉とあまり変わりませんね・・・
参考:『三才山にて』
http://highlyeffective.naganoblog.jp/e339680.html
Hitoshi Yonezu at 15:22
| 日常生活
2009年11月04日

今朝はある異業種交流会の例会のゲストとして参加してきました。
朝7時半から、全力でお話をしましたので、もう体が活性化しており、長い一日を有意義に使えそうです。今日は仕事で、上田→長野→東京→上田と移動します。
写真は上田市内のあるお寺の銀杏の木です。昨日撮影しました。
黄色の葉っぱと、青空と、白い雲、白塀のコントラストがあまりにもまぶしかった。
自然の美しさは不思議ですね。
人気ブログランキングの投票サイトです。私のブログがみなさまのお役に立てましたら、クリックをお願いいたします。

Hitoshi Yonezu at 10:00
| 日常生活
2009年10月31日

この秋、信州では、きのこがとれないようです。
知人のきのこ採り名人は、雑きのこは30年に一度くらいの不作だと言って嘆いていましたし、ある飲食店では、店主の方が、いま地元の松茸はありません、と釈明をされていました。
当社でも、9月半ばから松茸の仕入価格が急騰したので、おかしいなと思っていました。やはり、モノがないようなのです。
松茸はそれ自体はそれほどおいしいものとは思いませんが、香りを楽しむことや、松茸を食べるという行為自体が、日本の秋らしくて、心をかきたてます。
りこぼう、紫しめじ、くりたけなどの雑きのこは、豚バラ肉とともにきのこ鍋にするとおいしいです。私は雑きのこのほうが好きです。

きのこが不作だと、さみしいですね・・・
(写真は、今年の焼き松茸と松茸鍋です。)
人気ブログランキングの投票サイトです。私のブログがみなさまのご参考になりましたらクリックをお願いします。

Hitoshi Yonezu at 11:04
| 日常生活
2009年10月30日

昨日は、RCの仲間で隔月に開催しているワイン会がささやにて行われました。
インドにワインがあることをご存知でしょうか?
インドといっても、ワインのイメージがわかないでしょうが、素晴らしい作り手がいるのです。最近では有名レストランにも採用され始め、すごい勢いで成長しているそうです。
発泡酒一種類、白一種類、赤三種類と、五種類のワインを飲みました。どれもおいしかったです。
ワインリスト
①スラ・ブリュット・メトッド・シャンプノワーズ
②スラ・ソーヴィニヨン・ブラン
③タイガーヒル・メルロー
④スラ・レッド・シラーズ
⑤シャトー インデージ シャンデリ カベルネ 2007

ささやのお料理のメニュー
オードブルとして
プロシュートとホワイトアスパラのピクルス
エダムチーズとインカのめざめロースト
ボイルポークの黒胡椒風味
野菜の三色テリーヌ ヤリイカとオリーブのマリネ 寒ブリのワサビ風味のマリネ
海老パンロール、長芋、さつま芋のフリット
目鯛のポワレ トマトフロマージュソース
オーストラリア産牛リブロースのステーキ りんごのバターソース
パン
おいしいワインとおいしいお料理で、そこにいる人たち全員が楽しく盛り上がり、幸せな気持ちになって、心が豊かになりますね。
人気ブログランキングの投票リンクです。私のブログが御参考になりましたら、クリックをお願いいたします。

Hitoshi Yonezu at 10:36
| 日常生活
2009年10月28日

昨日、出張で松本へ向かう途中、三才山峠で撮影したものです。
上田方面から松本へ向かう場合、三才山の料金所を出て、小さなトンネルを抜けると、橋を渡ることになります。
その橋の先は三才山トンネルに向かって緩やかに上りながら、自動車が山に吸い込まれるような形で道路が続いています。
トンネルを抜け、橋を渡るときの風景は、視界一面に、若葉、深緑、紅葉、枯葉、荒涼、雪と季節毎に様相を変えて、ワーッと迫ってきます。
まるで巨大な絵のようです。
トンネルを抜ける時に、今日はどうなっているのかな~と楽しみに通っている、私の好きな場所です。
私としては信州の名風景(というものがあれば)に推薦したいですけどね・・・
写真はあまりきれいではないですが、三才山トンネルの直前の場所です。昨日の三才山の紅葉の雰囲気だけ見て頂きたいと思いました。
人気ブログランキングの投票サイトです。私のブログがみなさまのご参考になりましたらクリックをお願いします。

Hitoshi Yonezu at 10:00
| 日常生活
2009年10月27日

信州人ならば、いまごろ、つけばやっているの???と思われるでしょうが・・・
週末、東京から5人のお客さま(全員が中小企業診断士の経営コンサルタントの先生方)が研修のために信州上田においでになりましたので、私の友人が経営するつけばにお連れしました。
つけばとは、初夏から初秋にかけて、千曲川の河岸に小屋を建てて、そこでとれる鮎などを食べさせる飲食店のことをいいます。
今はもうシーズンは終わりかけて、落ち鮎の時期になっていますが、昨年も同時期にお客様をお連れしたことがあり、喜ばれましたので、時期外れとはいえ、今年もお連れしたのです。
10月25日は、そのつけばの今年最後の営業日でした。
東京にお住まいのみなさまですので、小さめの上品な鮎しか召し上がったことがないそうで、上田の滋味あふれる鮎の塩焼きに、無言でかぶりついておられました。
一瞬あまりにもシーンとしたので、一人の方が、
「カニを食べているときみたいだね」
とおっしゃいました。まさにその通りでした。
塩焼き、田楽、お刺身、てんぷら、唐揚げ、鮎こく、鮎飯などを召し上がりながら、鮎の骨酒がみるみる空になっていきました。
都会の方に川魚は大丈夫かな~と心配しておりましたが、皆さんに大喜びしていただき、うれしかったです。(鯉西の西沢さん、ありがとうございました。)
人気ブログランキングの投票サイトです。私のブログがみなさまのお役に立てましたら、クリックをお願いいたします。

Hitoshi Yonezu at 10:03
| 日常生活
2009年10月26日
5時20分 起床 ジュース作りなど
6時50分 新幹線あさま号で上田駅から東京へ出発(読書、ジュース)
9時 日本橋N社訪問
10時 東京駅八重洲口地下街の喫茶店にてH氏と面談(アイスコーヒー)
12時 ランチ(オムライス)
13時 東京駅近くの某ホテルにて経営の勉強会
17時 終了
18時 中目黒駅近くの店舗にて視察会と試食会(お刺身など) M氏
19時30分 終了
20時 新宿駅からあずさ号で松本へ向けて出発
(社内にて書類整理、読書、カキフライ弁当、春巻き)
23時 松本にて社内MT
25時30分 終了
25時40分 ホテル着(ブログ執筆など)
26時30分 就寝
人気ブログランキングの投票サイトです。私のブログがみなさまのお役に立てましたら、クリックをお願いいたします。

Hitoshi Yonezu at 10:00
| 日常生活
2009年10月25日
昨日このブログでご紹介した光永覚道師のお話の続きです。
参考:『京都にてユース会』
http://highlyeffective.naganoblog.jp/e337334.html
仏さまなどにお祈りするときに、お寺でも家のお仏壇の前でも、下を向いて静かに祈っている人が多いのですが、この方法では、仏さまは気がついてくれないそうです。
師によれば、チンとかゴンとか鳴らすものは、「私がここいますよ」ということを、仏さまに気づいてもらうためのものだそうです。
音を鳴らして、仏さまが気付いてくださったところで、朝は今日自分がやりたいことを確認し、夜は一日の活動をご報告をするのがよいそうです。
仏さま、如来さま、菩薩さまなどは、まるで眠っておられるかのように、半眼で静かに下方を見ておられます。
お寺で鐘をゴン!と鳴らせば、仏さまが「はっ!」と驚いて、お参りにきた人に気がついてくれるという説明をされた時には、聴衆が爆笑しておりました。
みなさんが納得し、よい話を教えてもらったと喜んでいました。
人気ブログランキングの投票サイトです。私のブログがみなさまのお役に立てましたら、クリックをお願いいたします。

Hitoshi Yonezu at 10:00
| 日常生活
2009年10月24日

ある銀行の勉強会(ユース会)が京都市で行われた。全国から1,500名を超える経営者が集まった。
堀場製作所最高顧問の堀場雅夫さんが基調講演をされ、そのあと分科会に分かれて勉強をした。
分科会では比叡山延暦寺南山坊のご住職である光永覚道師の「回峰行いま人はどう生きたらよいか」というお話を伺った。
光永氏は千日回峰行を満行され、北嶺大行満大阿闍梨であられる。前にこのブログでご紹介した、やはり大阿闍梨であられる酒井雄哉師の下で修業され、その姿をみて千日回峰行に臨まれたという。
ご参考に:『一日一生』
http://highlyeffective.naganoblog.jp/e305504.html
光永師のお話によると、過去があり、未来がある。いま生きている我々の存在は、過去から未来へのつなぎでしかないそうだ。つなぎであるこの刹那を積み重ねていく。
この刹那をベストに行動して、終わったら、結果がベストでなくてもよい、ベターでよかったと思う。この繰り返しだそうだ。
写真は交流パーティーの冒頭のお祝いとして行われた祇園甲部伝統儀式「手打ち式」の様子である。
京都にはこういう日本の伝統的なものがたくさん残っている。こういうものをコツコツと守っていることは素晴らしいと思う。応援したい。
火の用心カチカチ(卑近な例示で恐縮です)のように、歌に合わせて木を打っていることは分かったが、歴史的な意味はよくわからない。
それでも興味深く見ることが出来て、もっと見てみたいなと思った。
人気ブログランキングの投票サイトです。私のブログがみなさまのお役に立てましたら、クリックをお願いいたします。

Hitoshi Yonezu at 10:05
| 日常生活
2009年10月22日
時代によって言語は変わっていくものだそうですが・・・
この10年くらいの間にメールでコミュニケーションをとるのが当たり前になって、日本語の言葉遣いもずいぶん変わってきたと思います。
携帯電話のメールでは、絵文字や顔文字だらけのメールを受け取ることもあります。
また「こんにちわ(こんにちは)」とか、「東京え行きました(東京へ行きました)」とか、知らないで間違っているのか、わざとこういう言葉を遣っているのか、よくわからないこともあります。
社内の報告メールでも顔文字を使う人がいましたが、ビジネスコミュニケーションと個人のコミュ二ケーションの区切りがつかなくなっているのです。
反省する内容のメールでこんな顔文字が来たら、受け取った人はもっと頭に来てしまうのはないでしょうか。
m(_ _)m
学生や若いアルバイトたちの個人的な連絡ならば、仕方ないと当初は思うのですが、ビジネスの中でこのままにしておいては、正しい日本語を遣えなくなり、コミュニケーションが破綻し、最後には美しい日本語が消滅してしまうと思い、だんだんと直していかせます。
このように考えること自体が古いのかもしれませんが、私にはまだ納得できておりません。
試しにメールの文章を工夫するための書籍も読んでみましたが、表面的なテクニックだけ学んでどうなのだろうかとあまり共感できませんでした。
( 一一) (;一_一) (--〆)
人気ブログランキングのリンクです。私のブログがお役に立てましたら、クリックをお願いします。

参考文献:『たった一通で人を動かすメールの仕掛け』 浅野ヨシオ (青春出版社)
Hitoshi Yonezu at 10:02
| 日常生活
2009年10月20日
朝食でもランチでもいいから、絶えず機会を逃さず誰かと近づきになろう。たとえ今日うまくいかなくても、週末までにあと六回、誰かに会う約束が出来るではないか。
(『一生モノの人脈力』より引用)
人脈を増やすために誰かと食事をするのはまさにその通りですが、それだけを考えなくても、少なくとも、一人で食事をするよりは、誰かと食事をしたほうが、ずっと楽しくなります。いろいろな話をすることが出来ますし、そのお店の話題や食事の感想を共感することもできます。
時間が決まっていることもよいです。食事の終わりの時間になれば、そこで自然と区切りをつけられるからです。ティータイムのように漫然と時間を過ごしてしまうこともありません。
冒頭の文章はアメリカ人の書いた本からの引用ですから、人脈を広げることについてはかなり積極的です。
飛行機で隣にアメリカ人が座ると、こちらの都合など構わず、どんどん話しかけられますよね。日本人もそういう面は少し見習ってもいいのかもしれません。
私の父はもう70歳を超えていますが、当社の経営するお店で、私の知らない方と食事をしている姿をよく見かけます。
いくつになっても面倒くさくなることがなく(信州の言葉でいえば、「いくつになってもずくがあり、」)、自ら好んで、誰かを気軽に誘える・・・そういう感覚は大切だと思います。
人気ブログランキングの投票サイトです。私のブログがみなさまのお役に立てましたら、クリックをお願いいたします。

参考文献:『一生モノの人脈力』 キース・フェラッジ (ランダムハウス講談社)
Hitoshi Yonezu at 10:00
| 日常生活
2009年10月19日
杞憂とは、無用の心配をすることです。
中国の杞の国に、天が落ち地が崩れて、身の置き所がなくなるのではないかと心配し、夜もられず、食物もろくに食べられない人がいた、という故事からきています。
別の日本語でいえば、取り越し苦労(とりこしぐろう)です。
この世の中、いろいろなことが起こり得るでしょうから、大事にならないための備えは必要です。
しかし、起こってもいないことを想像して、くよくよ心配するのはいかがなものでしょうか。心配をして、頭がそのことばかりになってしまうのは、時間がもったいないです。
私も昔は、経験不足で未熟だったので、杞憂=取り越し苦労ばかりしておりました。いまでは、変な心配はしなくなりました。その時に考えればよいと思うからです。
よいことを想像して、楽しい気持ちになったり、気持ちを高ぶらせたりするのは、とてもよいのですけどね・・・
人気ブログランキングの投票サイトです。私のブログがみなさまのお役に立てましたら、クリックをお願いいたします。

参考文献:『三省堂中国故事成語辞典』 金岡照光 (三省堂)
Hitoshi Yonezu at 10:00
| 日常生活
 小泉元総理大臣のお話を伺う機会に恵まれました。
小泉元総理大臣のお話を伺う機会に恵まれました。 昨日は上田商工会議所の賀詞交換会、一昨日は上田三田会の新年総会が開催され、この後もいろいろな新年会が目白押しです。
昨日は上田商工会議所の賀詞交換会、一昨日は上田三田会の新年総会が開催され、この後もいろいろな新年会が目白押しです。 ささやでは、今朝6時からおせち料理づくりに大忙しです。
ささやでは、今朝6時からおせち料理づくりに大忙しです。
 昨日は、お客さまにご一緒して、日本酒の会に参加してきました。
昨日は、お客さまにご一緒して、日本酒の会に参加してきました。

 RCのお客さまと、二か月毎に開催している「ワインを楽しむ会」が昨夜ささやにて開かれました。
RCのお客さまと、二か月毎に開催している「ワインを楽しむ会」が昨夜ささやにて開かれました。




 ホテルの屋上から近くのマンションを撮影しました。実際に見ると宝石のようにきれいなビルなのですが・・・
ホテルの屋上から近くのマンションを撮影しました。実際に見ると宝石のようにきれいなビルなのですが・・・
 今朝、松本から上田へ移動する途中で撮影しました。三才山峠付近です。
今朝、松本から上田へ移動する途中で撮影しました。三才山峠付近です。 今朝はある異業種交流会の例会のゲストとして参加してきました。
今朝はある異業種交流会の例会のゲストとして参加してきました。
 この秋、信州では、きのこがとれないようです。
この秋、信州では、きのこがとれないようです。

 昨日は、RCの仲間で隔月に開催しているワイン会がささやにて行われました。
昨日は、RCの仲間で隔月に開催しているワイン会がささやにて行われました。 ささやのお料理のメニュー
ささやのお料理のメニュー
 昨日、出張で松本へ向かう途中、三才山峠で撮影したものです。
昨日、出張で松本へ向かう途中、三才山峠で撮影したものです。
 信州人ならば、いまごろ、つけばやっているの???と思われるでしょうが・・・
信州人ならば、いまごろ、つけばやっているの???と思われるでしょうが・・・


 ある銀行の勉強会(ユース会)が京都市で行われた。全国から1,500名を超える経営者が集まった。
ある銀行の勉強会(ユース会)が京都市で行われた。全国から1,500名を超える経営者が集まった。


