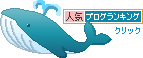「支那」という言葉は、いまの中国では蔑称として受け取られ、NGワードとなっているが、本来は賛美でも蔑視でもない中立の言葉だったそうだ。
古代インド人がサンスクリット語で中国のことを「チーナ」と呼んだものに、漢訳仏典で、支那、脂那、至那などの漢字を当てて音訳したことが元になっている。
日本では日清戦争以降、「支那」という言葉に侮蔑的なニュアンスをこめることが多くなったが、高杉晋作や石橋湛山や芥川龍之介など、そういう意味合いをこめずに使っていた日本人は多かったし、清朝末期に清朝打倒を目指していた革命派の中国人は「清国人」を呼ばれることを拒否し、好んで「支那人」を自称していたという。
中華という言葉は世界の中心に花が咲くという、いわゆる中華思想を示しているのだが、これを日本はなかなか認めようとしなかった。
英語でいうところのChinaは、つまり「チーナ」、「支那」のことだからと、1930年ころまでの日本は、「大支那共和国」という独自の呼称をわざわざ案出し、中華という言葉を使わなかったのだ。
同じ漢字文化圏であるにもかかわらず、中華と呼んでくれないところに、中国は日本の悪意と屈辱を感じたのだ。
日本の右寄りの論壇の中には、いまだに「支那」という言葉を使う人がいる。
私はこのあたりの経緯をいままでよくわからないでいたが、『貝と羊の中国人』を読んで、中国人の気持ちがよくわかった。
その他にも、例えば中国人がなぜ国境海域の天然ガスを勝手に掘ってしまうのか、日本人にはなかなか理解できないところだが、この本を読めばその精神性が理解できる。
これから東アジアの同じ漢字文化圏の国として、日本と中国はもっと分かりあっていかねばならないだろう。
分かりあったほうが絶対に双方の利益になる。
長い歴史の流れの中に日中関係がある。最新のニュースばかりを見ていても、分からないことがあるのだ。
中国を理解するために、日本人としてぜひ読んでおきたい本だ。
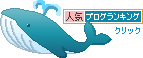
参考文献:『貝と羊の中国人』 加藤徹 (新潮新書)
Hitoshi Yonezu at 10:00
| 読書感想