『俳句とエロス』は、ふだんはあまり目に触れることのない官能的な俳句を、文学的に詳しい説明を加えながら紹介してくれています。
著者の復本一郎さんは、プロフィールによれば、2005年時点において、神奈川大学の教授で、文学博士です。ご自分も俳句をつくっておられますし、俳句に関する著書もたくさんあります。
俳句というと、「わび」「さび」や、花鳥風月を詠むというイメージが強いと思いますが、中には、客観的に異性美を追求した「エロティシズム俳句」というものがあるのです。「エロティシズム俳句」は、異性間の感情を詠う「恋愛俳句」とも違いますし、人間の性の営みを謳歌する「破礼句」、「艶笑俳句」とも違うものです。
「エロティシズム俳句」を意識的に作り始めたのは、日野草城(1901-1951)という俳人だそうです。この方は有名な俳人ですから、みなさまも名前はご存知かと思います。
明治から昭和にかけて、今ほど言論が自由ではなかった時代に、俳句とはいえ、このような表現がよくできたものだなあと思います。
エロティシズムといっても、「エロい」という直接的なニュアンスとは違います。想像の中で感じる微妙なものです。
この本からいくつか引用いたしますね。
合(あい)の宿お白い臭き衾(ふすま)かな 夏目漱石
春の灯や女は持たぬのどぼとけ 日野草城
やははだのはしばしみゆる夏衣(なつごろも) 日野草城
あねいもと性異なれば香水も 吉屋信子
人の手に髪ゆだねゐる薔薇の午後 西尾榮子
解説はのせないでおきますが、いかがでございましょうか。もう少し過激なものもありますが、このくらいにしておきますね。
明治も、昭和も、いまも、エロティシズムはそうそう変わってはいないのではないでしょうか。
花鳥風月を詠う普通の俳句と同様に、五七五の短い言葉の中に、微妙なエロティシズムを表現できるのは、日本の俳句だけではないかな~と思います。
俳句の知られざる一面をとらえた興味深い本です。季節感だけの俳句になじめない方は、この本を読んでみてください。
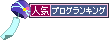
参考文献:『俳句とエロス』 復本一郎 (講談社現代新書)
Hitoshi Yonezu at 10:00
| 読書感想